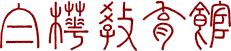227. 恋知エピソード1 Love of thinking
1991年 討論塾 討論会
ー 竹内芳郎・竹田青嗣・武田康弘 ー
竹内芳郎(故人、1924年 - 2016年)は、「注1.講壇哲学者たちの説く<現象学>や<実存哲学>にたいして、かぎりない侮蔑と憎悪を抱く人たちだけを、己れの読者として選んでいるのだ.」と語る孤高の哲学者(國學院大學フランス語教授)です。サルトル、メルロ=ポンティらの訳者・解説者でもあり、若かりし頃の武田康弘(白樺教育館館長)の師でもありました。
竹田青嗣は今なおもっとも売れている哲学書の著者です。1991年当時はまだ新進気鋭の文芸批評家で、『現象学入門1989年』を書いたあとでした。武田はそれを高く評価し、竹内芳郎に紹介しました。人間のあらゆる活動の土台となる認識の原理(難解な現象学)をわかりやすく記述した竹田の著作は、しかし、能動的思想とは異なるために、両者を合わせることで新たな世界が拓けるのではないか、その可能性を考えて討論を企画し、実行したのでした。
以下に紹介するのは、1991年2月17日と、5月19日、および11月10日に開催された「討論塾」の記録(塾報)です。人のあらゆる活動の土台となる「認識の原理(現象学)」について、社会問題に取り組むときに必ず直面する対話(討論)成立の可能性について、現在なお大きな課題となっている問題の深く抉るような討論です。なお、この塾報の文責は、武田康弘です。
今なお、意味深い貴重な討論と思いますので、以下に載せます。
加えて、武田が、竹田青嗣を竹内芳郎に紹介する前の経緯=「竹田青嗣さんとの対談」と、「竹内芳郎さんとの出会いと交際」も添付します。興味深い出会いの物語です。
6.および7.は武田による竹内批判、竹田批判と言えるものです。この討論塾での討論は、後の武田による「※恋知(=哲学)提唱」へと繋がるひとつの契機となったのでした。
8.は竹田青嗣の名著「言語的思考へ」の書評(Amazonへの書き込み)です。参考までに。
1.討論塾 塾報 26 1991年2月17日 「社会批判の根拠」
2.討論塾 塾報 33 1991年5月19日 「自我論と真理論」
3.討論塾 塾報 46 1991年11月10日 「現象学の意義」
4.竹田青嗣さんとの出会いと対談 1990年7月23日
5.竹内芳郎さんとの出会いと交際 2022年4月9日
6.体験(明証性)から出発する哲学 ―「具体的経験の哲学」批判Ⅱ― 2011年10月20日
7.竹田青嗣さんの哲学書読みとしての哲学について 2022年4月18日
8.解題的紹介 竹田青嗣著「言語的思考へ」 2001年4月
※
第2版第1刷 PDFファイル(7.4MB)ダウンロード=>クリック
(両面印刷を前提とした構成になっています。)
竹田青嗣さんの哲学書読みとしての哲学について 2022年4月18日
思想・哲学の読書趣味としては、史上最強なのが旧友の竹田青嗣さんの著作でしょう。分明で、かつ推理小説のように読者を引っ張りますので、愛読者が多いです。
ただし、あくまでも「生きられたフィロソフィー」ではなく、『※言語的思考へ』です。対して、わたしの哲学は、イマジネーションを重視し、現実に応答する哲学です。
それだからでしょうが、彼の読者は、現実問題にはあまり興味を持ちませんし(高校教師をしているが教育問題には関心はない、と彼の読書会に参加する熱心な竹田ファンは言いました)、社会活動をしていた人は、彼の本を読むことで問題が解決!?してしまい、実践的活動はしなくなります(笑・ホントウ)。
見事なまでに個人としての人間から牙を抜く哲学読解ですから、平和が訪れます(笑)。みな既成の秩序内に収まり、保守派にはありがたい哲学となっています。彼はイラク戦争を支持しましたし、「学校は国家空間であり、生徒や教師の自由はない」とする『プロ教師の会』の本を朝日新聞で称揚しました。現実問題については、テレビや新聞を見て判断すると言い、自分で調べることはしないと言います。また、日本社会は、このままで、左右に振れなければよいと討論塾で話していましたので、改革とは無縁です。
哲学本の読解に優れている竹田さんは、現実の社会問題には疎く、かつ関心が薄いのです。「哲学は100年の計で考えるので」というのが、わたしとの共同の仕事(参議院行政監視委員会調査室客員調査員)での発言です。彼はわたしが企画実行した1991年の討論塾での討論会の後で、自信を付けて文芸批評から哲学専門になりましたが、それと共にイマジネールや直観的な世界から離れていきました。
哲学は言語ゲームであると宣言する竹田さんは、西洋の哲学書を読むことを趣味とするとも語っていましたので、現実の人間(自他)の生や教育や社会のありようを考え、諸問題に応答しようというわたしとは大きく違います。わたしが提唱し実践してきた恋知(Love of thinking)とは異質です。
以下は、以前に「竹田教授の哲学講義」について書いたアマゾンレヴューです。
ギリシャ哲学と近代ヨーロッパ哲学についての解説書として、本書は秀逸です。
哲学書の読解が、思想の本質を探るという「意味論」として提示されていて、深く納得できます。
各哲学説の核心的な内容を軸としての解説本であり、一般教養としての哲学の履修にも、哲学を専攻する学生にも、一押しの「教科書」です。
また、竹田さんの哲学の解釈は首尾一貫して大河のようであり、ギリシャ哲学と近代ヨーロッパ哲学のもつ価値を闡明にしますので、哲学教師にも大いに参考になるはずです。
(注意)
けれども、竹田さんとは違い純然たる哲学科教授で、ハイデガーやポンティなどの翻訳者でもある木田元さんの意味論としての西洋哲学通史=「反哲学史」とは見方の違いも大きいので、それも知らないと片手落ちになりますが。
ただ、注意しなければならないのは、竹田解釈が現代に生きる人(特に若者)の日常感覚に見事にフィットするために、竹田さんとそのグループによる哲学書読解の成果(現在進行中の「完全読解」シリーズ等)を後追いする営みが、「哲学する」の代わりになってしまうことです。
日々、自分が生きている現場・現実において、自分の生を自分で考え・つくる能動的営みこそ「哲学する」ことなのですから、哲学書の読解を「生きて哲学するエロース」と混同しないように注意すべし!です。それを意識して読まないと、ただの「哲学書オタク」になってしまいます。
大学の哲学教師でない大多数の人にとっては、自分の日常の「仕事」「生活」を踏まえて、生の意味や価値を考え・生きるのですから、哲学は、それに役立つように遇さなければ意味がありません(哲学が人生をスポイルしたのでは、笑えない笑い話)。
実はここからが本題なのですが、わたしは竹田さんとは旧知の仲で参議院ではわたしがお誘いして一緒に仕事をしましたし、昔昔、彼の優れた「現象学理解」を後押しする催しを我孫子市で開催しましたし、竹内芳郎さんとの討論会を企画して3回実現させましたが(他に、わたしが中心の会にも2回参加)、彼がずっと続けている哲学書の読書会は「言語・論理ゲーム」としての哲学で、実践を含む広大なフィロソフィ―(恋知)の世界ではない、という認識を竹田さんらは持っていないのです。そこが困りもの、とわたしは思い、幾度もその違いを闡明にするように伝えてきました。
「言語ゲームとしての哲学」に限定することが哲学という態度が、いつまでもサルトルを理解→了解できない深因でもあると思います。
以下に簡明に俯瞰してみましょう。
キリスト教会は、ギリシャ哲学を換骨奪胎することで膨大な神学体系をつくりました。スコラ哲学と呼ばれますが、その改革として出てきたのが17世紀のデカルトに始まる近代西ヨーロッパ哲学です。西欧の学問を明治に直輸入した日本では、哲学といえば、この思想を指しますが、それでは一面的な思想の見方になります。「神学の改革としての哲学」と言えども、よく知られている通り、デカルトは代表作の「方法序説」の二部では、神の存在証明を書いています。
近代西欧哲学は、本質的にキリスト教の世俗化としての理論体系ですので、スコラ哲学がめがけたもの=人間存在と世界の全体をトータルに解明し叙述しようとする意思を受け継いでいます。そのために、理論は複雑で難解となる宿命をもち、言語の構築物としての論理の体系となり、カントからへーゲルに至るドイツ観念論でピークに達しました。人間存在と世界の全体をトータルに解明し叙述するというのは、宗教のご宣託のようなものでない限り出来えない不可能事ですが、その出来えないことの努力を続けたのが西欧の「近代哲学」だとも言えます。その歴史は、20世紀最大の哲学者といわれたハイデガーが1966年に行ったシュピーゲル対話で幕を閉じたと言えるでしょう。
シュピーゲル対話では、ハイデガーは、哲学にはもはや何も期待できないと言い、従来の哲学の地位はサイバネティクスが占め、諸科学が哲学の替わりをする、と主張しました。哲学は無力だと繰り返し述べ、われわれ人類にできることは、何百年後かに現れる「神」のようなものを待つだけだ、と言いましたが、これは、ハイデガーの存在論(人間と世界のトータルな解明)の挫折であり、「哲学の敗北宣言」と言えます。
17世紀に始まり20世紀に終わったのが西欧近代哲学と言えますが、この西欧哲学(キリスト教という一神教がバックボーンにある)は、ルネサンスの運動で明らかなように、古代エーゲ海文明への憧れに端を発していて、ギリシャのフィロソフィー(恋知)を換骨奪胎してキリスト教神学をつくり、その上に乗ったものでしたから、相当な無理の上に建てられた思想の建造物であったわけです。
21世紀以降のフィロソフィーは、「言語的世界へ」(竹田言語論の結語)ではなく、イマジネールに着目し、言語の呪縛を超えて、でないと困ります。広大な想像力次元への着目で新しい世界を拓くには、恋知=Love of thinkingという発想と態度への転回が必要です。優れた論理の演繹を更に延ばせばよい、ではないのです。
2011年4月1日