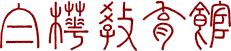227. 恋知エピソード1 Love of thinking
1991年 討論塾 討論会
ー 竹内芳郎・竹田青嗣・武田康弘 ー
竹内芳郎(故人、1924年 - 2016年)は、「注1.講壇哲学者たちの説く<現象学>や<実存哲学>にたいして、かぎりない侮蔑と憎悪を抱く人たちだけを、己れの読者として選んでいるのだ.」と語る孤高の哲学者(國學院大學フランス語教授)です。サルトル、メルロ=ポンティらの訳者・解説者でもあり、若かりし頃の武田康弘(白樺教育館館長)の師でもありました。
竹田青嗣は今なおもっとも売れている哲学書の著者です。1991年当時はまだ新進気鋭の文芸批評家で、『現象学入門1989年』を書いたあとでした。武田はそれを高く評価し、竹内芳郎に紹介しました。人間のあらゆる活動の土台となる認識の原理(難解な現象学)をわかりやすく記述した竹田の著作は、しかし、能動的思想とは異なるために、両者を合わせることで新たな世界が拓けるのではないか、その可能性を考えて討論を企画し、実行したのでした。
以下に紹介するのは、1991年2月17日と、5月19日、および11月10日に開催された「討論塾」の記録(塾報)です。人のあらゆる活動の土台となる「認識の原理(現象学)」について、社会問題に取り組むときに必ず直面する対話(討論)成立の可能性について、現在なお大きな課題となっている問題の深く抉るような討論です。なお、この塾報の文責は、武田康弘です。
今なお、意味深い貴重な討論と思いますので、以下に載せます。
加えて、武田が、竹田青嗣を竹内芳郎に紹介する前の経緯=「竹田青嗣さんとの対談」と、「竹内芳郎さんとの出会いと交際」も添付します。興味深い出会いの物語です。
6.および7.は武田による竹内批判、竹田批判と言えるものです。この討論塾での討論は、後の武田による「※恋知(=哲学)提唱」へと繋がるひとつの契機となったのでした。
8.は竹田青嗣の名著「言語的思考へ」の書評(Amazonへの書き込み)です。参考までに。
1.討論塾 塾報 26 1991年2月17日 「社会批判の根拠」
2.討論塾 塾報 33 1991年5月19日 「自我論と真理論」
3.討論塾 塾報 46 1991年11月10日 「現象学の意義」
4.竹田青嗣さんとの出会いと対談 1990年7月23日
5.竹内芳郎さんとの出会いと交際 2022年4月9日
6.体験(明証性)から出発する哲学 ―「具体的経験の哲学」批判Ⅱ― 2011年10月20日
7.竹田青嗣さんの哲学書読みとしての哲学について 2022年4月18日
8.解題的紹介 竹田青嗣著「言語的思考へ」 2001年4月
参考:
柳宗悦と竹内芳郎に共通する問題(=知識人としての構え)に触れた論考があるので
以下に紹介します。
=> 市民の知を鍛える - 竹内哲学と柳思想を越えて -
※
※
オリジナルでは話者名の記述が文末になっていましたが、読みやすくするため文頭に変更してあります。
古林 治 2009年1月5日
第2版第1刷 PDFファイル(7.4MB)ダウンロード=>クリック
(両面印刷を前提とした構成になっています。)
2.討論塾 塾報 33 「自我論と真理論」 1991年5月19日 (1991年8月15日作成)
5月19日の第34回討論会は、2月17日の29回討論会(「発想の転換-社会批判の根拠」塾報26)の続編として再び竹田青嗣さんを問題提起者に立て、言語・哲学問題について行われた。テーマは、〈自我論と真理論〉(『具体的経験の哲学』(竹内著、岩波)の第2論文「現象学的言用論のためのエスキース』を下敷きにして)である。
参加者は、阿部憲一、阿見拓男、石曽根四方枝(事務局)、大黒一正、奥田暁子、小坂井和良、佐藤ユミ子、佐野力、杉山巌、鈴木一郎、鈴木太一、竹内芳郎、武士剛、竹田青嗣、武田康弘、中土井鉄信、広瀬大地、根本行雄、皆川効之の19名。進行係および文責は、武田。
武田:
きょうは、去る2月17日の討論会において主に竹内・竹田間で問題となった、『真理』と『自我』をどう捉えるかをめぐっての討論を行います。まず竹田さんが「現象学的言用論のためのエスキース」をレポートしてきていますので、それから始めることにします。
(竹田さんのレポートは、P.14 [後述]にあります。)
武田:
竹田さんの「まとめ」を聞いていてひとつ気になったのは、竹内言語論の特徴=核心点だと思える「言語の階層性」の捉え方が暖昧なことです。
竹内:
うん、そうです。言葉の使い方(機能)の違いに注目して、私は言語の階層化の理論を作ったのです。第二次言語(広義のメタ言語 - 理論言語と文学言語)は、日常言語の疎外(コミュニケーションの挫折)によって初めて出てくる。アーベルやハーバマスは、もっとも彼らに限らずヨーロッパの言語学者はほとんどみなそうですが、すべての発話を論証的討論に収斂させてしまい、発話行為におけるコンテクストを無視してしまう。これは、言語の階層性に無知なことと結び付いている問題なのです。
竹田:
それは分かりましたが、その他の点については私のまとめでいいですか?
竹内:
概括的にはいいかもしれないが、つつけばいろいろある。例えばコギトーの扱いかたなども問題だが、それをやっていると大変なので、事前に竹田さんが出されていた質問(P.15を御覧下さい。)にお答えする中で、そうした問題にも触れてゆきたいと思う。
竹田氏の問題提起への回答①〔この部分の文責は竹内〕
私の本にたいする竹田氏の問題提起は、A「言用論」に関するものとB「現象学」に関するものとに二大別でき、しかもそれぞれ四項目づつに分かれているようだが、さし当たってまず、言用論に関する最初の二項目のご質問にお答えしておきたい。
Ⅰ
まず私の言用論研究の「目標」だが、私のこの研究はこれだけ独立したものではなく、『言語・その解体と創造』に始まる多岐にわたった私の言語研究の一環、その現在における一到達点でしかない。では、総体と しての私の言語論の「目標」はと言えば、それはあの本の「はじめに」 に明記しておいたように、現代を人類文化総体の危機として捉え、その危機を打開する「文化革命」の課題にたいしてまともに答えられるような言語基礎論を構築すること(何しろ、この頃の私には、人間文化の基礎を形成しているものは言語だと感じられていたのだから)、同時に、こうした文化の危機のさなかを生きる「口舌の徒」=知識人の生存の根拠をも明らかにする、つまり、現代において「書く」とはどういうことか?の問いにもまともに答えられるような反省的言語理論を展開すること、であった。しかもこの二重の課題を、「初版まえがき」に記したように、私たちの日本語および日本文化の固有の特性から来る特殊な問題性を深 く踏まえながら追求してゆくこと、であった。その結果得られた理論的成果が、すなわち「言語階層論」および「階層流動化論」であったわけ だ。(これはdiscommunicationを踏まえたcommunication論という私の言語論が固有に具えているある逆説性が必然に産み出す立体的構造だ)が、これは当時はまだ明確化できなかったにしろ、今から考えれば明らかに言語総体における「発話」次元での理論的成果であって、その意味で私は初めからすでに、「発話の言語学」としての「言用論」にぞくする仕事をしていたわけだ。
私はこの言語論のあとで『文化の理論のために』という文化論の仕事をするようになり、そこで人間文化の基底を形成しているものとしての 「想像力」のあらたな発掘があり、人間固有の言語活動を下から支えているのも実はこの想像力だということが解ってきた。では、想像力によって支えられた言語とは何かと言えば、それは、「メタファーを核とした言語像」ということになり、では、メタファーの成立するのは言語のどの次元かと言えば、これまた「発話」の次元だということになり、こうしてこの視角からも発話の言語学としての「言用論」が浮かび上らざるを 得ぬこととなった。
実際、一口に言語と言っても、文化論(『文化の理論のために』岩波) 第四章で明らかにしたように、「語」、「文」、「発話」の三次元は絶対に混同を許さぬ異質の次元であり、そのうち最後の次元こそ言語の生きて働く最も具体的な位相、したがって、私の基礎的な哲学的立場としての「現象学」が、私の言うように「具体的経験の学」だとすれば、言語に関する現象学的研究は、必然に「言用論」ということになるはずであリ、この点からしても、私の言語学探究が言用論へと注いで行ったことは、まことに当然だったわけ。
Ⅱ
つぎに「言語学」との関連だが、私は近代の学的世界に成立した個別諸科学の領域区分なぞ全く信用しておらず、したがって今まで、自分個人の関心の赴くままに、つねに「脱領域的」な研究を行ってきた。それだけに、自分の言用論的研究が、既成の個別科学としての「言語学」を刷新するものなのか、それとも相対化するものなのか --そんなことを気にしたことは一度もなかった。ただ、個別科学としての言語学自体の最近の趨勢を眺めていると、ソシュールから構造主義言語学までは、大体において「語」次元の言語学だったのが、チョムスキー以後はすっかり「文」次元の言語学に主流が移り、その後はまた「談話の文法」などといった「発話」次元の言語学が登場するようになってきた--
この言語学内部の一般的趨勢に私の研究もほぼ照応している、とは言えるように思われる。
〔竹内〕
竹田:
大体のところ今の竹内さんの言用論に異議はありません。では私が言語学に対してどう思っているか、その芯について少し話します。 ソシュールを始め幾人かの言語学者の本を読んで感じたのは、「言語本質論」がないということです。彼らが言語について語るのは、近代言語学を「学」としてきちんと体系化しようという意図からのようですが、ぼくはそうした言語学的発想そのものに異和を覚えます。言語を還元して行けば最後に残るのは「意味」ですが、言語学者のように言語の意味を規則の体系として形式化しようとするのは不可能事です。簡単に言えば、自分の感じる痛みと、「イタイ」と発語した言葉との断絶の問題です。「イタイ」と発話したとたん私の固有のいたみは消えてしまう。言葉はデジタル的で有限なものの差異によってしか表せないために、自分の言わんとすること(内言)と原理上必ずズレてしまう。この言葉の本質論をきちんと追求しているのは、フッサールの『論理学研究』だけです。なぜ自分が(広義の)メタ言語を使って他人や社会と関わっていくのかというような問題は、言語学のレヴェルではいくらやっても分からない。だから私は、言語学に抗して言語の問題を考えてきたのです。それを竹内さんは、文化革命の視点から考えられているようですが。
武田:
そう、思いは重なりあっているのです。
竹内:
そうですが、ただ「言語学」というのはすべてダメだとは言い切れない。とても変遷が多いのです。だからフッサールだけが言語の本質を解明したと決めつけないで、もう少し余裕のある態度でいた方がよいでしょう。
竹田:
それは分かりますが、ただ言語学という構えにはどうしても異和を感じます。
武田:
近代主義的な「学」の世界を、現象学的な視線の変更によって実存論的に見直すということですね。
竹内:
それはよく分かる。
竹田:
現代の言語についての最大の問題は、「意味は言葉によってきちんと確定される。だから言葉を正しく積み重ねていけば確実な認識に至る」と考えるか、それともデリダのようにそれを否定して「意味と言葉とのつながりを断ち切っていく」方向で考えるのか、という点にあると思う。
竹内:
私は近代科学としての「言語学」なぞを擁護するつもりは全くないが、あえて言語学者になり変わって言えば、あらゆることを概念化してしか表せないというのは言語学の最初の常識。「イタイ」という私の実感=黙せるコギトーと言葉とが直接結び付かないというのは、言語学の自明の前提。言語学に限らず近代の個別科学は、人生全体の実存的な問題からその一部を切り取ってその枠内でのみ真偽を問うものだ。デリダのやっていることなぞは言語学とは言えない - となるでしょう。
竹田:
正にそういうふうに切ってしまうところに、私は言語学の問題を感じるのです。メタ言語に関心のある人はみな、言葉によって一体どこに行き着くのだろうか、ちゃんとした認識に到達するのか?それともコップの中で動き回っているだけで何の合意も作り出せないのか? こういう疑問を持っていると思う。だからこそデリダのような思想がリアリティーを持つのです。ぼくはデリダには与しませんが、言語の本質論=「意味と言葉の問題」を深く煮詰めていくことが、思想問題の大きな転換を果たすことになると思います。言語学者が、「そんなことは自明の前提で何をいまさら・・・」というとしたら、それこそが問題でしょう。言語学(個別科学)は、自らが設定した枠・約束事 がどういう基礎を持っているかを考えなければダメで、それをしない なら学問そのものに意味はなくなります。
竹内:
それは全くその通りです。
竹田:
私たちが言語について考えるのは、「言語を使うことの人間にとっての実存的な意味本質を追求するためだ」というところでは一致していることが分かりました。
武田:
では竹田さんの質問への答えの続きとして、「言用論」に関する残りの二項目についてお願いします。
竹田氏の問題提起への回答②〔この部分の文責は竹内〕
私の本にたいする竹田氏の問題提起は、A「言用論」に関するものとB「現象学」に関するものとに二大別でき、しかもそれぞれ四項目づつに分かれているようだが、さし当たってまず、言用論に関する最初の二項目のご質問にお答えしておきたい。
Ⅲ
残りの二項目のうち、A-3の「真理」問題は後まわしにして、まずA-4のハーバマスらの言用論研究との連関をとり上げよう。たしかに、私は彼らの言用論の展開にたいして、次のようなかなり多岐にわたる、しか もかなり根本的な不満をもっている--
-
彼らはすべての対話をひたすら「論証的討論」に収斂してしまうような理論構成をとっており、そこから第一に、発話行為における「発話場」の軽視、私のいわゆる「言語階層論」への盲目性が生まれ、第二に、発話場からの超越を固有の使命とする「理論言語」ですらそれ独自の発話場形成を必要とするということへの無自覚性が生まれ、その結果、結局は旧態依然たるロゴス中心主義=近代的合理主義の枠内にとどまる言用論でしかないこと。
-
言語的コミュニケーションを考察するにしても、言語以外によるコ ミュニケーションの諸形態をも広く大きく視野に収めてそれを行うべきにもかかわらず、それをすっかり怠ってしまっていること。
-
発話行為のもつ価値性に着目したのはよいが、それをすぐさま規範化する前に、まず発話の原初形態としての「欲望に根ざす他者への訴えかけ」〔拙著100ページ参照〕にまで深化させてそれを捉えておくべきなのに、それをしていないこと。
-
人間言語のもつ本質的な虚偽性、および、その虚偽性の自覚的な選択によるその虚偽性の逆説的超克の試みとしての「文学言語」の特性、への全き盲目性。
-
「対話」のもつ各人の差異性、相互否定作用にたいする看過。
-
「黙せるコギトー」の無視、および「発話次元におけるコギトー」についての具体的考祭の欠落。
以上は、私の本のなかでも指摘しておいた彼らにたいする様々な不満点だ(これらは、その後に読んだハーバマスの大著『コミュニケーション行為の理論』のなかで、部分的には解消したものもあるが、やはり根本的には解消されずに残ってしまっている)が、こうした数多くの不満点にもかかわらず、彼らが「論証的討論」に内在する倫理的規範性を明確化し、それによってあらゆる対話、談話のなかでの「討論」なるものの固有の特性を刻印してくれた点は、いつまで経っても「討論」の大義に目覚めることのないわれわれ日本人にとっては、やはり貴重だと言わねばならない。
まず、彼らのいわゆる「理想的発話状況」とは、事実として実現されていることはむしろ稀であるにもかかわらず、討論的対話が討論的対話として成立するためには反事実的にせよ、必然に想定せざるを得ぬ発話の本質的条件であり、しかもそれが同時にまた、今ある社会構造を公正なものにまで変革してゆくための倫理的な要請目標ともなっており(「理想的発話状況」はそのまま同時に「理想的生活形態」)、こうしてカントではバラバラになっていた理論的理性と実践的理性との合一がはかられ、またそのことによって、「民主主義」の実現にとって「討論」というものがいかに不可欠の契機であるかが明確化されるにいたった。私はこ の点は高く評価する。
第二に、彼らは真理問題を認識対象と認識主観との関係の問題に限定してきたカントから新カント派に至るまでの真理論の地平を大きく突破し、(この点では現象学の動向とも相唱和しつつ)発話における「命題」の位相に真理論を論定しつつ、明瞭に真理合意説の立場に立ちながら、しかもそれでいて合意すべき「他者」を反事実的に永劫の全人類にまで理念化することで、同時にコンフォミズムの愚劣に堕することをも回避したこと。これも少なくとも基本的には支持できる方向性で、ここから最後に、言用論における「真理」問題への突破口が開かれる。
Ⅳ
つぎにA-3の「真理」問題だが、たしかに、真理は客観的実在の問題ではなく、他者とのコミュニケーション行為としての発話のなかの、しかも「命題」部分にのみかかわる価値であって(「黙せるコギトー」はむろんのこと、「発話次元でのコギトー」つまり行為遂行的動詞または以=言辞行為の主語も真理価値とは無関係)、それゆえ、必ずしもあらゆる発話において真理価値が重要な意味をもつとはかぎらない。ただ、「命題」部分が発話のなかでドミナントとなる「討論的対話」においてだけは、真理価値の要請は不可欠であって、そのことを否認したら、もはや討論は不可能となってしまう。
たとえば、親友や恋人とのあいだでお互いの意見や趣味の異同を単にたしかめ合って対話しているような場でなら、いずれの主張が「正しい」かなぞ、はじめから問題とはならぬ。なにしろその異同の確認をつうじて、お互いの親密度を深め合うことがこの対語の唯一の目的なのだから。ところが二人のあいだで「討論」的対話が交されるようになると、お互いの主張のあいだの異同の確認は、とたんにいずれが「正しい」かの真理性をめぐる争いへと転化変質するのであって、そうならないような対話は、およそ「討論」的対話とは言えない。ところがこの間の質差が極端に薄れてしまったのが現代日本の思想状況であって、これは私の本の P.111以下の付記に書いたとおり(「真偽」問題の「趣味」問題への還元)。そしてこの質差を明確化してくれる点では、ハーバマスらのあの狭隘な論理的・倫理的規範主義も、われわれ日本人にとっては貴重な「地の塩」 たり得る、というのが私の意見。
とはいえ、ここで言う真理性は、討論を討論として成立させるために反事実的に、しかし必然に要請される理念的規範性であって、どこかに不動・永遠の絶対的真理のかたちで実在するようなものではない。したがって、塾報26P.10にあるような、あらかじめ引かれた線路の上のどこかの駅のようなスタティクなイメイジで構想されるごときものではない。むしろ、討論塾開設マニフェスト〈二〉に記したような、真理の絶対主義と相対主義とをともにのり越えられるような、他者のみならず自己をも相対化し批判することのできるような「超越性原理」として働く一つの理念なのだ。
実際、人類思想史上にはじめて普遍宗教なるものが胎動し、それによってはじめて超越性原理なるものが登場してくるようになって、またはじめて人間のコミュニケーション史上に「討論」なるものも、「真理」の追求とともに姿をあらわしてきたように思える(たとえばインドの「ウパニシャッド」から仏教や「六師外道」の時代、中国の「諸子百家」時代、ギリシャの「哲学」形成期)。この討論塾でも、機会ある毎に普遍宗教の意義を、ふりかえるようにしているのもこの故であって、そういう意味で、ピラトがイエスに向かって「真理とは何か」と問いかけるヨハネ福音書の記述には、何かしら深い象徴的意味が感じられるのだ。なにしろ、人類がまだ原始共同体や国家共同体のなかに抱きかかえられて、そこから自立していない間は、共同体内の慣習にしたがった利害調整だけが問 題で、「真理」もそれを前提とした「討論」も必要がなく、そうしたものから裸形の個人として人間が析出されるようになってはじめて、それを支えるものとして真理や討論的対話が要請されるようになったのだから。こうしたものは、決して人類のコミュニケーション史の初めからあったものではないのだから、その発生事由をよく明察して、その現代的意義を考えてみる必要があるのだ。
〔竹内〕
武田:
では、二時限目を始めるにあたって、議論をよく噛み合わせて深めるために、なぜ竹田さんが「真理」の捉え方を変える必要を執拗に問題にするのか?その背後にある思いを話して下さい。
竹田:
私は現代社会の問題を解決していく上で、従来のマルクス主義的な、更に言えば党派的な考え方が、非常に大きな桎梏になっていると感じています。だからいっぺんすべて更地に戻して、「妥当(合意)をどう作り出すのか」、その方法を考え直す地点から再出発する必要があると思う。今度竹内さんの「言用論」(『具体的経験の哲学』第2論文) を読み直してみて、私と同じモチーフを持っていることが分かりまし たが、中心的な問題である「真理」の捉え方については前回(2.18) 同様、ピンと来ないのです。
正しい言語使用を積み重ねていけば真理に至るというギリシア時代以来の伝統と、皆が正しいと言うことが正しいのだという同調主義の双方が、ともにおかしいというところまでは一致していると思うが、ではどのように「真理」を捉えたらよいのか?それがよく見えないのです。
簡単に私の考えを述べておきます。「覆いを取リ除くことで隠されている道を発見する」という従来の真理観は、全くおかしい。さまざまに異なる思いの人間が、「共生」していく必要から、言葉を編み上げてゆく作業が始まるのだが、この「言葉」の出現によってはじめて「真理」は問題となる。そこで核心となるのは、「人間は互いに関係を持ちながら生きていく他はない」ことの納得で、そこから個々人は「対話」によって妥当(合意)を導いていくプロセスの重要性を了解する。この前提があってはじめて相互主観的に「真理」は編み上げられていくことになる。 --こんな感じです。
根本:
竹田さんの話はよく分かりますが、ただ実際には、学校教育やマスコミなどを通じてその社会に特有の世界像を強制される面も強いと思う。
竹田:
それはその通りですが、どんな社会でもそれがなくなることはない。ただその社会特有の考え方でうまくやっていけなくなった時に、自分の中のその一枚目の価値観(考え方)を、メタ言語によって間い直してみる動機がおとずれるのです。
根本:
それは分かりますが、それだけ言っていては、いつまでたっても出発点に留まるのではないですか。現実の社会では、様々な権力によって人間関係が規定されている。
竹田:
しかし、その権力的な人間関係を変えていくにも、変えていこうとする人々の間での妥当(合意)をつくり出すことがまず必要になるはずです。
(注) この問題については、『塾報26』のP.11上L.1~下 L.8を参照。
根本:
だが、世界には血みどろの闘いや悲惨がたくさんある。
竹田:
「だから、あなたのような悠長なやり方ではダメだ。」と言いたいのでしょうが、私はずっとその問題を考えてきて、そうするより池に方法はないという覚悟というかフンギリをもって言っているのです。
竹内:
「真理」の話に戻して言いますが、妥当を導くという竹田さんの話 は、経験的レヴェルでは全くその通りですが、その経験を成立させる 「理念」的次元についても見ておく必要があると思います。もちろん 「形而上学的真理」ではなく、討論という言説が成立するために構造そのものとして含まれる規範性、そういうものとしての「真理」を想定することの必要性です。一例をあげると「我執を去る」ということ。ただ「納得」というと、欲得のレヴェルでそうしていることもあるが、その次元を越えて自分の誤りを率直に認めて修正する自己批判の精神=「真理性」の前での謙虚さを要請するものとしての「理念」が討論には必要でしょう。「真理性」の前で「我」を引っ込めたときの喜び(ベルグソンの区分ではjoie=歓喜)は、自分の要求が通ったときの喜び(P1aisir=快楽)とは違う。今までの自分から脱皮する喜びがあるわけで、この質差を見ておくことは重要だと思う。
竹田:
おおよそは納得できますが、いま竹内さんの言われたことは、「討論」だけではなく、もっと広く「対話」全般についても言えることだと思う。
ただ一つ疑問に感じるのは、P.88(『具体的経験の哲学』)のハーバマスの「理想化された他者」(「自分の人生が人類史と同じ拡がりをもつと想定したとき・・」)の想定。これではカント的「理念」に限りなく近づくことになる。
実は私は、いままで竹内さんの言う「理念」もカント的なものではないか?と思っていましたが、今日の話を聞いてそうではないことが分かりました。「我執を去る」とか「自己批判」という「理念」は、私の哲学の根本原理である「エロス性」に似たものだと思えます。
--人間は自己拡張のエロスをもっているが、それとは別に真・善・美によって自分の殻が破られることのエロスもある。ここで大切なのは、人類(史)などの「理念」を先に置き、そこからの倫理的要請として他人や社会を考えるのではなく、逆に、人間は自己のエロスにこだわるからこそ(そこでの挫折から)それを越えた「関係性のエロス」へ向かうのだということ--です。
武田:
両者の思想の芯は共通なのです。
竹内:
ええ。ただ私は「エロス」の質の違いをおさえる必要を言っているのです。
竹田:
それは分かります。
鈴木一:
竹内先生の言う理念は、普遍宗教とのからみで出てきたものではないですか?
竹内:
そう、人類に「真理」なるものを思いつかせたのは、人類史的には 「普遍宗教」の功績です。
竹田:
「普遍」を最初に考えるのはやはりまずい。あくまで個々人が生きるうえで何が大切なのかをつなぎ合わせていって、その先に「普遍」や「理念」を導き出していくという順序で考えるべきだと思う。
竹内:
私もハーバマスのような「規範主義」を批判しているのであって、 「理念」を先に置くことはしない。本にも書いておいた通り、「発話」 の原初形態は、欲望に根ざす他者への訴えかけなのです。根は「欲望」にあるわけで、「真理」問題はそこに根ざしているのですが、しかし 「真理」という概念に到達するまでには、人類は長い歴史を迫らなければならなかった。普遍宗教が成立したのには、それだけの社会的条件があったのです。
武田:
竹内さんは、歴史的現実として普遍宗教のもたらした功績と意義を指摘しているだけであって、「普遍」を先に置くことをしているわけではないのです。
竹田:
ああ、分かりました。その点は私が誤解していました。では、竹内さんは、ハーバマスのいう「自分の生涯が人類史と同じ拡がりをもつ」という想定については、どう思われますか?
竹内:
自分の身の回りに現実にいる他者だけに限って対話していたのでは、同調主義に陥る恐れがつよい。彼らはそれを避け「他者を理念化」するために、こういう反事実的な想定をしたのであり、私は評価している。
竹田:
私はこういう想定はイヤなのです。これだとどうしても人類全体をはじめに置くことになってしまう。
竹内:
いや、彼らにも「真理合意説」は前提としてあって、その上でこう いう理念を打ち出してきているのです。
竹田:
ハーバマスらが規範主義的になるのは、個々の人間の実存からの出発ということを徹底させていないからだと思う。そのために社会全体(人類全体)で合意できるような何かがあるはずだという構えになってしまう。
武田:
竹内氏の指摘する、彼らの規範主義・論理中心主義の源泉は、実存の原理の不徹底にあるということですね。
竹内:
ああ、そうですか。・・・
竹田:
ぼくが物事を考える順序は、個々人の実存のエロスが出発点になって、そこにこそ様々な普遍性や理念の根拠があるとする。そうしないとどこかで必ずひっくリ返ってしまう。
竹内:
その通りなのだが、それは根本さんも言っていたように、出発点にしかすぎないのではないか?
竹田:
それが最大の問題なのです。ある理念の具体的な出発点がどこに根拠をもっているのか?それをちゃんと言えば問題は解決する(終わる)。それが「原理」の問題なのです。ぼくが竹内さんの本を読んで、大部分は一致しながらも一つ不満なのは、その出発点があいまいで、普遍性や理念をどこから導こうとしているかがよく見えないことです。
阿見:
真理の問題を言うとき、竹内さんは「論証的討論」の場についてのみ語っているようですが?
竹内:
その場でしか「真理」は問題にならないからです。
阿見:
その点に竹田さんと竹内さんの違いがあります。
武田:
そうです。討論だけでなく、もっと広く日常生活の場のなかにも「真理」(さらには善・美)の問題があると、竹田さんは見ているのです。
竹内:
ああなるほど。
阿見:
ですから、竹内さんの本にある「喜怒哀楽の地平にまでついに降リ下ることのない理論は、精緻さを誇れば誇るほどますます空しさを募らせるぱかりであろう。」という言葉に従うとすれば、竹田さんの思想の方がよりー層徹底していると思えます。竹内さんの「真理」は、作業仮設としての概念のようです。つまり、我執を去るため・コンフォミズム(同調主義)に陥らないための装置のようなものと思える。
竹内:
ああ、そうかもしれません。
阿見:
実存の内側から見ていくなら、「我執を去る」という言い方よりも、 「関係性のエロス」と言った方がよいと思えます。なぜなら竹内さんの言い方では、そこから段々と広がっていくというふうにはならないで、却って出発点に留まってしまう恐れがあるからです。
武田:
私の考えを述べると、徹底して「我」にこだわることが大切。自分を最も愛することが大切。本当にそこを立脚点にして生きつづけると、竹内さんの言葉では「我執を去る」ということ、竹田さんの言葉では「関係性のエロス」ということが出てくるのです。
竹田:
ええ、ぼくもそうだと思います。独我論を徹底させていったときに独我論は破れるのであって、はじめに独我論がまずいから「関係性」を立てようとすると、必ず外から倫理的な要請を持ち込まなければならなくなってくる。そうすると社会の問題も内的には考えられなくなる。
武田:
「教育」実践をとおして実証的にも言えることだが、自己のエロスにこだわることを善きものとして肯定することがなければ(残念ながら現実にそのように子育てをしている親はほとんどいないが)、こども(人間)が本当に内的に飛躍することはない。
竹内:
そのことは承認します。しかし、竹田さんの「現象学が方法論的に独我論的な構成をとらねぱならない」という主張は、フッサールのす ぐれた研究家P.リクールも認めているように哲学的に言って成立しない。人によっては、自我が先に立たないこともありうる。「自我」も「他我」も共に世界のなかにある外的な一実体にしかすぎない。純 粋自我(各人の具体的経験)が、双方を成立させているのだ。
竹田:
経験的な意味での「自我」は、もちろん他人との関係のなかで出来てくるのであって、それは、ぼくも認めています。
ぼくは、「言用論」ではなく「欲望論」としてずっと考えてきました。人間は生まれたときは癒合的で、自我も他我もありません。 赤ちゃんはあるとき、自分の思い通りにならなくても泣かずに「我慢」することを覚えるが、それは「我慢」したときに「よい子ね。」とほめられるからです。人間の欲望(エロス)は本質的に幻想的なものであり、それはだんだんと「自己」へと中心化されていくのです。このように「欲望論」として考えると、経験的な次元での「自我」が先か「他我」が先かという問題は、ほとんど意味をもちません。
竹内:
では、17ぺ一ジの注にあるワロンの考え(幼児は「他者体験」が先)についてはどう思いますか?
竹田:
発生論的(=経験的)にはその通りでしょう。しかし、それはいま問題にしていることとは関係がありません。人間は、自分自身にたいする「自己像」がエロスになり、それは一生つきまとう。はじめに他者を立てて、「人間の根本は〈関係〉にあるのだ」といったのでは、全く説得力がありません。自己のエロスがどこにあるかを探り、そこ を基準にしなければ、「関係」を切りとる尺度もなくなります。「起源」と「本質」の問題は違うのです。
竹内:
私も、関係を先に置く〈広松渉〉のような構えはとっていません。だから、「どんな場合でも各自性を失うことはできない。」と書いているのです。ただ、竹田さんのように「エロス」イコール「自己愛」と置くのは問題がある。欲望(エロス)は、他者に向かっても自己に向かってもよいので、まず「自己」への欲望があって、次に「他者」への欲望に転化すると言うのはまずい。
竹田:
竹内さんはぼくの言わんとすることをつかんでいません。私の用語法がうまく入っていないために、こうした批判が出てきてしまうのでしょうが。・・・
きょうは、「自分の人生や他人・社会との関わりの真・善・美を求める一番おおもとの根拠をどこに置けば、さまざまに異なる人間が互いに妥当を導き出していけるのか?」それをずっと議論してきたわけですが、ぼくは、何らかの倫理や規範を出発点にする旧来の考え方(先に「要請」を置く)では、社会問題の解決も全く不可能だと考えている。どうしたら自分自身が楽しく・豊かに・おおきなエロスを持って生きられるか、というところに出発点を求めなくてはならない。
竹内:
それはその通りで私も認める。
武田・
竹田:
それだったら一緒で、対立点はないのです。
竹内:
少しちがうのは、さっきも言ったように、エロスといっても「joie=歓喜」と「P1aisir=快楽」の質差があるので、それをおさえることだ。例えば「科学」は人間の生活を安楽にする=P1aisirを満すことだけを考えている。宗教的なconversion(回心)や芸術がもたらしてくるものは、それの自己否定があって、そのとき生命の本源に早急する強烈なjoieが得られる。
竹田:
ベルグソンの「歓喜」と「快楽」の二分法は、形而上学的だとは思うが、言わんとするところはよく分かります。
竹内:
「個我」にとらわれていては、P1aisirしか得られないのだ。
竹田:
いや、そういうふうに二つに分けられるものではない。さまざまなエロスを概念的に二つに分けて、これは○、これは×、などと考えて生きている人がいたら、その人の人生は少しも生き生きとしていない。そうではなく、自分がこうしたいと思うそのエロスをどう了解して生きていくか、そのエロスが自分の生にとってどんな意味をもつのだろうか?を考えてみることが重要なのです。
広瀬:
それはよく分かりますが、では、「討論」には一体どんな意味があるのでしょうか?
竹田:
討論をするためには、多少とでも通じ合うところがあると思えることが前提です。もちろん「批判」は大切なのですが、相手の真意をくみとろうという姿勢がまるでないというのでは、「討論」のみならず、すべての「対話」は成立しないでしょう。何かしらのエロス的通い合いがなければ、なにかを生みたせるという希望はもてません。だから、「きちんと正しく言葉を使えば分かるはずだ」というハーバマス (竹内さんの本で知る限りでの彼ですが)の言い方は、ひどい楽天主義に思える。どんなに反対されても、またなかなか通じ合えなくても、相手が一生懸命に考えて話しているのが分かれば、その誠意はぼくを打ちます。そういうわけで、自分の考えをみなの中に投げ入れて試すことのできる「討論」には大きなエロスがあるのです。
武田:
そのように解した「エロス」であれば、竹内さんも異論はないと思いますが。
竹内:
ええ、ないですよ。
皆川:
エロスには、奴隷と主人とのエロスや復讐するエロス、三島由紀夫の天皇へのエロスなどもあると思うが、どのようにしたらそうしたエロスを批判できるのか?その中にはまりこんでいたら、批判・脱却はできないのではないか?
竹田:
原理的には、自分で「自分のエロス」を問い直すことです。自分の感受性を絶対化して、即自的なエロス(三島でいえば「天皇が好きだ」) に拘っていたらダメで、それが自分のどこに根をもっているかを考え、また他者に試してもらうことで刷新していくのです。いままでもっていた自分のエロスが破られることには、とても大きなエロスがあるのですから。
竹内:
人殺しにエロスを感じる人間もいる。だからその質を問題にしないといけない。
竹田:
誰が問題にするかです。自分で問題にできなければ終わりです。
武田:
強制ではなく、内発的に間い直すことができなけれぼ、どうしようもないということでしょう。
竹内:
問い直したくない人もたくさんいる。
竹田:
それはどうにもできません。「理論」とはそういうものです。個々の人間の生が何であるかについては言えますが、生き方を監視することはできません。
竹内:
人間は、いやでもある種の価値判断は持ってしまう。
竹田:
そうですが、「オレはこれでいいんだ。」といって少しの疑問も持たない人がいたら、決して言葉は通じません。しかし人間はそんなに単純にできてはいない。新しいエロスを感じたときは、必ずそこに魅き つけられる。「言葉で認識はできない」という懐疑論がリアリティーをもたないのは、そのようにして人はみな、小さいときからだんだんと自分のエロスを開発して生きてきたからです。実存的に自分のエロスを深く育てていくというところから出発して、個々の人間は、「関係や社会」に達することができるのです。この出発点の原理を間違えると、昔やっていた党派的な考え方に必ず戻ってしまう。これがぼくの一番言いたいことです。
広瀬:
それはよく分かります。ぼくもその通りだと思います。
武田:
では、もう時間がありませんので、今日発言されていない方どうぞ。
武士:
具体的に「社会」を動かすにはどうしたらよいか?についても考えていきたいと思います。
佐藤:
竹田さんの考えを聞いていて、「背伸びしなくていいんだなあ」ということが分かりました。とても楽になりました。いろんな「ものさし」があっていいんですね。
阿部:
竹田さんの考え方だと、遅いようで却ってはやく世の中の変革もできるように思える(笑い)。
佐野:
「討論塾」だけで「真理」を見い出すというのは変な考えで、広く日常の生活のなかで、真・善・美を知るようにすることが大切だと思う。「この場でこそ真理を」とか「メディアを使って思想を発信せよ」とかいうのは無理がある。われわれ一人ひとりが、楽しく充実した生活をすることで、社会も変わってゆくのだろう。人が変わるのは、魅力ある生き方を知ることによってなのだと思う。
武田:
そう、ここもひとつの場ですよね。それに力を抜くと力がでるんですよ。
中土井:
「疑似エロス」のようなものからどうやったら抜け出せるのでしょうか?
竹田:
外部からやってこないような、内部だけ、自分の感受性だけに拘るようなエロスは必ず低減する。自分の中に閉じ寵もらずに広く求めようとすれば、必ずより大きなエロスがくる。しかし学生と話していると、手近なところで済まそうとして自己の小さな世界からなかなか抜け出せない。エロスを深めたり広げたりするのにもある種の技術がいる。もっと互いに踏み込んで話をして自分を広げる必要がある。
鈴木太:
ぼくは、いつも友達といろいろ面白いことをやってきたのだが、そういうのを哲学的には「エロス」というのだなと分かった。今日は、難しかったけれど面白かった。疑問に思ったことを家に持ちかえってまた考えてみたい。
大黒:
竹田さんの「現象学入門」は、とても分かりやすくてよかったです。今日はご本人にお会いできてうれしかったです。
阿見:
竹内さんと竹田さんの姿勢はすごく似ています。竹内さんの本はとても厳密ですが、分かりやすくて面白いです。今度聞いてみたいのは、「〈理想的発話状況〉における理想化された他者」というものが、具体的にはどのように働くのかということです。
武田:
そうした想定は諭理上の要請として出てくるのでしょうが、具体的な場でその考え方がどのように役立つのかを知りたいというわけですね。
では他になければ、時間ですのでこのへんにしましょう。
竹田:
今日話したおかげで、竹内さんの考えもずっとよく分かるようになりましたし、自分の弱いところも自覚できました。ぼくも今までずいぶん討論をしてきましたが、今日は相当にうまくいった討論会だったと思います。すごくあリがたかったです。
竹内:
違いがあるのはいいことですよ。差異も同一性も、「生産的」になるようにやってゆきましょう。また来ておおいに論じて下さい。
(*この討論会終了後、竹田青嗣さんは、直ちに入塾手続きを取りました。)
(注)
なお、ここで中心的な論点となった、自我と他我とコミュニケーションの問題については、滝浦静雄(盛岡短大学長)さんが、分かりやすい大変すぐれた本を出していますので、ぜひご一読下さい。『「自分」 と「他人」をどうみるか』(NHKブックス-596)のとくにⅢ他我の構成、Ⅳ自他の互換性と普遍性。 〔武田〕
*竹田さんの質問B(「現象学」に関する四項目)については、11月10日に行います。
【文責・塾報作成:武田康弘】
狛江討論塾
竹内芳郎著『具体的経験の哲学』より 竹田青嗣
「現象学的言用論のためのエスキース」レジュメ
*現象学の方法によって言語論的に「真理論」を考え直すというモチーフ
Ⅰ
- 現代の情報化社会において多様なメッセージ(情報)が氾濫しているが、この膨大なメッセージからどのように「世界」についての像を形作ればよいか、どのように「合意」を見出せるかという問題。・・・言語論への試み。
- J・ハーバーマス、K・O・アーベルなどの言語論の検討。
- 〈アーベル〉「超越論的言用論」の提唱。
- 「超越論的言用論」とはなにか。言葉は基本的に認識一般に対する「懐疑」や「批判」を可能にするものだ。しかし、そもそもこの「懐疑」や「批判」が有効であるためには、「それ自体は批判しえぬ」言葉のやり取りの条件が成り立っていなくてはならない。・・・要するに、どういう条件のもと.に、言葉は、正当に「認識」や「批判」の働きをもちうるのか、という基礎付け。
- 「超越論的言用論」をきちんとやると、正しいコミュニケーションのための「言語上の一般規則」だけではなく、適切な言語伝達が成立するための発話行為上の「倫理的規範」をも一緒に考えることができる。・・・さらにそれは、「人間のあらゆる倫理的規範の基礎づけ」にもつながる。
- 〈ハーバーマス〉「普遍的言用論」を提唱。「コミュニケーションにおけるあらゆる可能な相互了解のための普遍的条件」を探る。・・・社会的な人間関係の倫理的基礎づけにつながる。
ハーバーマスの「理想的発話状況」の三条件 - 責任能力をもった主体であること
- 発話に含まれた命題が真であること
- 抑圧のないこと
- 規則遵守において対等公正
- 四つの「妥当的要求」
Ⅱ
〈アーベル〉「超越論的言用論」、〈ハーバーマス〉「普遍的言用論」の問題点。
あまりに性急な規範主義的偏向。―――すべての談話を「論証的討論」へ収斂しがち
- コンテクストヘの考察足りない。
- ロゴス中心主義
Ⅲ
竹内現象学的言用論の提唱
- 言用論の有意義性
「意味が正しく通じる」「コミュニケーションが適切に成立する」、このことは単に形式的言語規範の問題ではなく、話者-間き手の相互関係の問題。 - 前言語的コミュニケーションの原理
言語活動の根本を「全生物のコミュニケーション発生史の過程」から考え直す。非言語的コミュニケーション活動への考察が必要。身体的表現の意味生産。 - 言語のフィクション性
「嘘」というコンテクスト。日常言語-理論的言語-文学言語。
果して、完全な「合意」というものはあるかどうか。 - 言語行為における「コギトー」の意味
「コギトー」をデカルト的「われ惟う」に還元していいか。
人生における一切の出会いを可能にする具体的経験としての「黙せるコギトー」。・・・各自性をもつ。「発話の次元におけるコギトー」とは。発話における「真偽」の条件を追いつめると、確実性はなくなる? - まとめ
交際的な発語の重要性。言語階層論の立体化。ディスコミュニケーションヘの視点。通言辞行為の考察。
前略。
5月19日の討論塾で、竹内さんの『具体的経験の哲学』所収の「現象学的言用論のためのエスキース」をレポートすることになっていましたが、武田さんから、できれば議論のためのレジュメを竹内さんの方にお送りしてほしいということでした。とても簡単なもので恐縮ですが、竹内さんにお聞きしてみたいことや、ぼくなりの疑問点などについて以下にまとめてみます。
A
- 言用論を、いま何のために、つまりどういうモチーフで問題にするのか。
その『目標』はどこに定められるべきか。 - 竹内さんの言用論は、現象学の相互主観性の概念によって言語学に新しいパースペクティヴをもたらそうとするものだと思えますが、それは言語学の新しい体系をめざすのか、それとも言語学それ自体を相対化することに力点がかかっているのでしょうか。
- 「真の了解」あるいは「真理」という概念をどのように理解すればよいか。
- 超越論的言用論の「目標」は、適切な「発話行為の倫理的規範」を打ち立てることにあるのでしょうか。つまり、ハーバーマスの基本目標に同意していいとお考えですか。それともこの基本目標そのものを批判するべきでしょうか。
言用論に関してはこういうことになりますが、そのほかに、竹内さんと僕とで多少ずれている点があるように感じました。
B
- 現象学が「絶対的真理」の基礎付けという「目標」をもっている、ということについて。
- 現象学が「ロゴス中心主義」である理由について。
- 現象学における主観性(自我)の重視を、なぜ、どのように”乗り越える”必要があるのでしょうか。
- 現象学の根本的な”意義”についてどうお考えですか。
*
現代のポスト構造主義にたいする現象学の意義などについては、とても 啓発され、同意できる点が多くありました。当日は、哲学になじみのない参加者にもなるべく理解できるようなかたちで話を進められれぱいいなと思っています。
僕の知り合いも一人か二人参加するかもしれません。どうぞよろしくお願いします。
早々。
竹内芳郎様
竹田青嗣