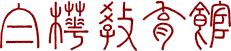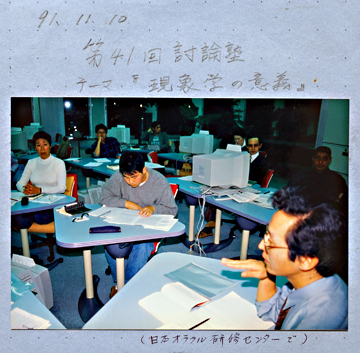227. 恋知エピソード1 Love of thinking
1991年 討論塾 討論会
ー 竹内芳郎・竹田青嗣・武田康弘 ー
竹内芳郎(故人、1924年 - 2016年)は、「注1.講壇哲学者たちの説く<現象学>や<実存哲学>にたいして、かぎりない侮蔑と憎悪を抱く人たちだけを、己れの読者として選んでいるのだ.」と語る孤高の哲学者(國學院大學フランス語教授)です。サルトル、メルロ=ポンティらの訳者・解説者でもあり、若かりし頃の武田康弘(白樺教育館館長)の師でもありました。
竹田青嗣は今なおもっとも売れている哲学書の著者です。1991年当時はまだ新進気鋭の文芸批評家で、『現象学入門1989年』を書いたあとでした。武田はそれを高く評価し、竹内芳郎に紹介しました。人間のあらゆる活動の土台となる認識の原理(難解な現象学)をわかりやすく記述した竹田の著作は、しかし、能動的思想とは異なるために、両者を合わせることで新たな世界が拓けるのではないか、その可能性を考えて討論を企画し、実行したのでした。
以下に紹介するのは、1991年2月17日と、5月19日、および11月10日に開催された「討論塾」の記録(塾報)です。人のあらゆる活動の土台となる「認識の原理(現象学)」について、社会問題に取り組むときに必ず直面する対話(討論)成立の可能性について、現在なお大きな課題となっている問題の深く抉るような討論です。なお、この塾報の文責は、武田康弘です。
今なお、意味深い貴重な討論と思いますので、以下に載せます。
加えて、武田が、竹田青嗣を竹内芳郎に紹介する前の経緯=「竹田青嗣さんとの対談」と、「竹内芳郎さんとの出会いと交際」も添付します。興味深い出会いの物語です。
6.および7.は武田による竹内批判、竹田批判と言えるものです。この討論塾での討論は、後の武田による「※恋知(=哲学)提唱」へと繋がるひとつの契機となったのでした。
8.は竹田青嗣の名著「言語的思考へ」の書評(Amazonへの書き込み)です。参考までに。
1.討論塾 塾報 26 1991年2月17日 「社会批判の根拠」
2.討論塾 塾報 33 1991年5月19日 「自我論と真理論」
3.討論塾 塾報 46 1991年11月10日 「現象学の意義」
4.竹田青嗣さんとの出会いと対談 1990年7月23日
5.竹内芳郎さんとの出会いと交際 2022年4月9日
6.体験(明証性)から出発する哲学 ―「具体的経験の哲学」批判Ⅱ― 2011年10月20日
7.竹田青嗣さんの哲学書読みとしての哲学について 2022年4月18日
8.解題的紹介 竹田青嗣著「言語的思考へ」 2001年4月
参考:
柳宗悦と竹内芳郎に共通する問題(=知識人としての構え)に触れた論考があるので
以下に紹介します。
=> 市民の知を鍛える - 竹内哲学と柳思想を越えて -
※
※
オリジナルでは話者名の記述が文末になっていましたが、読みやすくするため文頭に変更してあります。
古林 治 2009年1月5日
第2版第1刷 PDFファイル(7.4MB)ダウンロード=>クリック
(両面印刷を前提とした構成になっています。)
3.討論塾 塾報 46 「現象学の意義」 1991年11月10日 (1992年4月16日作成)
91.11.10(第41回討論会)。 テーマ‐「現象学の意義」。
問題提起者‐竹田青嗣、竹内芳郎。 進行係・文責・塾報作成‐武田康弘。
本討論会は、竹田青嗣を問題提起者とする3回目のもの。一応の完結編である。
(参考までに、第1回は、2.17の「発想の転換‐社会批判の根拠」、第2回は、5.19の「真理論と自我論」。)
当日の参考文献は、『具体的経験の哲学』竹内著(岩波書店)と『現象学入門』竹田著(NHKブックス)。および『塾報26』・『塾報33』。
参加者は、阿見拓男・石曽根四方枝・佐野力・島貫隆光・鈴木一郎・鈴木妙香・竹内芳郎・竹田青嗣・武田康弘・納冨昌紀・星野真理・皆川効之・綿貫信一の13名。なお会場は、佐野力が社長を務める渋谷の「日本オラクル㈱」研修センター。
まず始めに40分ほど竹内からの発言があったが、その部分は竹内本人がまとめたものをP.12 [後述]に掲載する。
竹田氏への竹内からの回答 Ⅰ
竹田:
竹内さんは今、『具体的経験の哲学』(岩波)の第一論文に書かれたことを繰り返して述べられましたが、ぼくはそれを読んだ上で、〈竹内さんの現象学理解〉を批判したのです{『現象学入門』(NHKブックス)}。 竹内さんは、そのぼくの批判に対しては全く答えていません。
まず言えるのは、フッサールは「絶対的真理」の基礎づけに腐心し たというのは、全くのウソだということです。竹内さんのみならず、多くの現象学者たちがそう言っているのはよく知っていますが、彼らは、フッサール現象学の核心を捉え損なっているのです。
フッサールは、自分の哲学はカントやへ一ゲルらのような偉い人が〈ある種独特の考え方〉を呈示するようなものとは違い、誰でもが 「妥当」を導いてゆけるような通路=道筋を示すことによって〈「学」を絶対的に基礎づける〉と主張していますが、これは確かにヘタをすると、なにか「絶対的真理」を求めているようにも読めてしまいます。
しかしフッサールは、前提として〈「客観」とは背理である〉と書いているのです。言葉によって「客観」を言い当てるという伝統的認識論を根本的に否定しています。「客観」は背理だと主張するフッサールが、「絶対的真理」を求めるなどということがあり得るでしょうか?
彼の言う「明証性」や「学を絶対的に基礎づける」ということは、「客観」とか「絶対的真理」への通路などではありません。ある条件が満たされると、人間の心には「確信」=「信憑がいやでもやってくる。「真理」や「客観」それ自体はないにも関わらず、「これは確かだ。」という確信が生じる。その一番底にある根拠のことを、「明証性」と呼ぶのです。だから「(絶対的)明証性」とは、「現実」それ自体の根拠なのであって、「(絶対的)真理」を構成するものなどではないのです。 {現象学入門」P.157-158を参照‐(武田)} 次に「学を絶対的に基礎づける」ということについてですが、これは「絶対的真理」とは何の関係もありません。「明証性」から段々と積み上げてゆけば「絶対的な学」に至るというのではなく、人間の心に確信がやってくる根拠は「厳密」に基礎づけられると言っているだけです。『危機』の中にもありますが、「学」というものがそれ自体で自立することは絶対にありえないのです。それは、生活の中での「確信」(明証性)に基礎づけられて始めて成立するものなのです。
以下は、フッサール著『ヨーロッパの学問の危機と先験的現象学』(短く『危機』と呼ぶことが多い)第34節よりの抜粋。(中公版P.494-497)〔武田〕
生活世界的に存在するものが問われているばあいに、それをまたもや客観的学の意味で存在するものとすりかえたりしてはならない。・・・生活世界の主観的な点と、「客観的」で「真の」世界との対比は次の点にある。すなわち、後者は理論的、論理的構築物であり、原理的には決して知覚できず、また原理的にその固有の自己存在について経験できないものの構築物であるが、他方、生活世界的に主観的なものは、すべての点からみて現実に経験しうる、という点でとくに区別されるという点にある。・・・思想上の構築物であっても、それが一般に真理を要求するかぎり、このような(現実に経験しうる)明証性に立ち帰ることによってのみ、真の真理をもちうるのである。この明証 性のもつ根源的権利をはっきりと主張すること、しかもそれが客観的論理的明証性に比べて認識を基礎づける、より高い品位をもつことを明らかにすることは、生活世界を学的に解明するにあたって、最も重要な課題である。客観的理論を形式と内容に従って基礎づけている客観的、論理的能作のあらゆる明証性が究極的に能作している生の中に、いかにそのかくれた基礎づ けの源泉をもっているかということが、完全に解明され、究極的に明証的にされねばならない。・・・われわれすべてが学校で習った客観学的な考え方に迷わされてたえずおかしがちなとりちがえから、われわれを解放するためには、めんどうな手続きが必要である。(下線とカッコは、武田)
竹田:
客観主義的な考え方からどうしたら解放されるかという、思想の 〈発想の転換〉を行ったのがフッサールなのです。その方法(現象学的還元)の核心は、なぜ自分はある確信を持っているのかを、自分の内側にある条件を検証することによって明らかにすることなのです。それを「方法的独我論」というのであって、フッサールは意識主義だというのは、全くのウソです。わざと独我論的な見方を徹底させることで、人間が知らずに持っている「独我論」を解いてゆくというのが、彼の方法なのです。
竹内:
竹田さんへの第一の反論は、「真理」と「客観」を一つの問題にしていることについてです。絶対的真理を客観にもっていかないというのが、デカルトに始まる大陸系(独、仏)の哲学なのです。確かにカントは、絶対的真理を求めたが、それを客観には求めていない。客観=物自体とは何だか訳の分からないものだ。それをきちんと整理するのが「主観」である。ただし個人の恣意的な主観ではなく、超越論的な主観、それが普遍的なのです。だからカントにまで来れば、絶対的真理と客観とは切れているのです。
竹田:
へ一ゲルはどうですか。
竹内:
へ一ゲルはまた転回します。客観的観念論。観念論ではあるが、カントのような主観主義ではない。
竹田:
確かにカントは、物自体=客観は認識できないとしましたが、実は暗黙のうちに物自体(客観)はあると想定していたのです。「客観世界」という考え方を捨て切れなかったために、もし神の持つような認識なら客観は認識できるはずだという恩いが残ったのです。だからカントを受けてへ一ゲルは、人間の認識能力に限界があるから客観は捉えられないのなら、限界がなければ捉えられるはずだとし、〈段々と高まってゆく認識能力〉という考え方をつくりだすことによって再び「客観」という概念を蘇生させてしまったのです。「人間の主観(意識)の内側の問題に限るならば全部言える」という、このカント哲学のすぐれた部分は逆転されてしまったわけですが、その原因はカントの不徹底さにあるのです。
竹内:
竹田さんのフッサール観についていろいろと疑問があります。 確かにフッサールは、真理の根拠は客観にあるとは言っていないが、〈客観を志向することなしに意識はない〉としたのは現象学の大きな功績です。だからある意味ではフッサールは、カントよりもずっと客観主義なのです。客観物を認識する場合の「射映」という考え方もそこから出てくるのです→違った角度から見ることで段々と認識は深まってはゆくが、不十全的だ。それに対して射映ではない内部知覚は十全的な認識が得られる、というのがフッサールの主張です。しかし超越論的還元による内部知覚にしても、決して十全的ではないことが分かってきた。そこでメルローポンティにまでゆく現象学の発展があったのです。その歴史をおさえなければダメです。
竹田:
いま竹内さんの話を聞いていて、フッサールを誤読していることがよく分かりました。例えば重要な概念である「射映」についてですが、竹内さんの捉え方ではカントと同じことになってしまいます。ここに物(客観物)があるから私に見えている、そう考えてはダメだとフッサールは繰り返し言っているのです。
竹内:
いやみんな外物なんだから、対象として客観物を措定しなければならないはずです。誰でもそうしていますよ。
竹田:
現象学の考え方の一番大事な点は、客観物を措定しないということなのです。
竹内:
知覚意識とは、対象を措定する意識のことです。措定しないというと、知覚を否定してしまうことになる。知覚というのは、自分の外にあるものを措定する意識のことをいうはずです。
竹田:
う一ん。措定という言葉の概念は・・・
武田:
自然的な見方では、当然「知覚物」は外に(始めに)あるわけですが、論理的には、外物の存在妥当は後から定立をうるのです。
(注)
想像や想起などと違い、外物(客観物)がいやでもやってくる意識体験のことを〈知覚意識〉と呼ぶのです。/私たちはふつう、まず客観物があってそれを五感によって知覚すると思っていますが、その客観物の存在を論理的に証明しようとすると大変ややこしいことになります。誰でもが自分の意識の内に閉じ込められているという原事実から逃れられないために、始めに客観があると置くと論理矛盾をきたすからです。そこで物事の存在の証明は、意識(主観)の内部での或る事情(さまざまな意識体験の中で、知覚意識だけは主観の自由にならないがゆえに、外なる存在を確信しないわけにはゆかなくなる)からしか、論理上は説明できないのです。〔武田〕
竹田氏への竹内からの回答Ⅱ P.14 [後述]をご覧下さい。
竹内:
ひとつ質問ですが、塾報33のP.10下にある、「自我の起源と本質の問題は違う」ということの意味についてお聞きしたい。
竹田:
自我の問題とは、分かりやすく言い換えれば、人間の自己中心性をどうやって乗り越えるかということですが、その解決のために、幼児は自我認識より他我認識の方が先だという経験的事実(起源)を持ち出しても意味がないということです。誰もがすでに持っている自我意識をどうするのか(本質)が問題なのですから。
竹内:
分かりました。/ 私は、経験的ではなく哲学的次元において〈自我〉などというものが必要なのかを問いたい。 私にとっての出発点は、自我ではなく「具体的経験」だが、それは他者にも自我にも出会う場なのです。だから「個人あって経験があるのではなく、経験あって個人がある」とした西田哲学は、その限りでは正しいし、サルトルの相剋にしても出会いの地平があって始めて成立するのです。もちろん自我はどうでもよいと言っているのではなく、それを根源的な哲学的カテゴリーとするのでは、近代哲学を越えることができないと考えるのです。
竹田:
いま竹内さんが言われたことには大きな齟齬はありません。たしかに経験があって「私」という意識が生じてくるのだとぼくも思っています。ただ一つ大事なのは、自我の問題と言っても、
①デカルトやカントやへ一ゲルらの哲学者と呼ばれる人たちが問題にしてきたことと、
②ふつうの人々にとって問題になっていることとは違うということです。ぼくも青年期には、サルトルの、「自我というものは意識の対象である ‐ そう考えれば自分も他人も同じだ」という言い方に感心したものです。若い頃は特に自分に拘るものですが、そういう時にサルトルの考え方はある種の解放感をもたらしてくれます。そこから更に「私はすでに世界の状況の中に投げ入れられている。だから、世界を深く知るようにすれば、自分(人間)の生きる意味は社会(変革)に参加することだ」という考え方にまで進むわけで すが、しかしこれは一部の学生やインテリには説得力があったとしても、ぼくの両親を含むふつうの人々にとっては説得力を持ちません。意識の対象として見れば、たしかに私も他人も同じです、どんな人でも「各自性」を持っていて、私という中心性から離れることはできないのです。誰でもが持つこの「自己中心性」というところに立脚して考えを進めなければ、哲学は実情からズレて観念化してしまいます。そうなれば納得をつくりだすことに失敗し、必ずどこかで、「こうあるべきだから、こう行為すべきだ。」を圧しつけるようなものとなってしまうのです。
竹内:
そう言うと、人間のあらゆる行為はエゴイズムから出ていることになるが、そうでない人間もいるのです。本当に愛他的な人も。
竹田:
愛他的な行為も、本当にそうしたいというその人のエロスから出ているものでなければ、ぼくは欺瞞性を感じます。
竹内:
私のエロス、とおっしやるけれど、私のをつけなければいけませんか。
武田:
私のを外せば、竹田さんの主張に同意するということですか。
竹内:
まあそうですが・・・/ まず自我を立て、そこからの感情移入によって他我を知るというのではなく、自分が見られているという被視体験が自我をつくるとした方がよいのです。具体的経験の中のドラマとして自他の相互入れ替わりの中から自我の構成を考えた方が哲学的にスムースな理論になると思います。/ またエロスにしても目がける対象があるわけですから、志向性を持ったものと考えなくてはダメです。エロスそれ自体が何かをするわけではないのですから。
竹田:
もし自我(純粋自我)を置かないとすれば、その志向性とは一体 なんですか?ぼくは、志向性の極のことを自我(純粋自我)とか主観とか呼んでいるのです。
竹内:
ないんですよ。無なんです。認識するときには「私」はない。あるのは志向している対象だけです。自我が出てくるのは、その認識関係をもう一度反省にかけた時です。ただその時にはまた認識する自分はなくなってしまいますが。
竹田:
フッサールのいう自我(純粋自我=超越論的自我)とは、竹内さんのいう対象となった自我(経験的な自我)について言っているのでは なく、志向性=何かに感じている主体のことを指しているのです。
竹内:
そういうもの(超越論的自我)はいらないのです。
武田:
整理すると、「おれは太郎だ。」というふつうの(経験的な)意味での〈自我〉を特権化しないところまでは一致しているわけです。問題はその先で、世界に意味付与する意識=何らかの対象を志向している意識の中心に「超越論的自我=純粋自我」を置く必要があるというのが竹田さんの主張であり、それは必要ないというのが竹内さんの考えなのです。
{(注)竹田さん(フッサール)のいう「純粋自我」とは、自我という名前がついていますが、実在物ではなく〈作用=働き〉のことを指します。外から与えられたものではない内なるはたらきそれ自体のことです。}
ただ経験的な自我を特権化しないという共通理解にしても、それが理論の次元やそこからの要請に留まらずに、どうしたら具体的現実の中で実現できるかを実情に即して探ることに最大のウェイトを置いている竹田さんと、理論(第二次言語)家としての使命に殉ずることを己れのレーゾンデートルだと信じている竹内さんとの間には、明示化しにくいのですが、大きな差があるようです。
鈴木一:
竹内さんは外部を重視し、竹田さんは内部を重視しているということですか。
竹田:
いや、外部を重視しないのではなく、外部は自己の信憑として成立すると言っているだけです。
鈴木一:
それはよく分かりますが、「普遍性」等の外部にある価値を否定するのはおかしいと思います。主・客問題は、西洋なら分かりますが、日本では大した問題ではないでしょう。「普遍性」や「絶対的理念」は、日本では必要です。だから、主・客問題を重視してエロスによって乗リ越えるという主張にはリアリティーを感じないのです。竹内さんのように外部に価値を設ける方がよいと思います。
竹田:
規範を作ることがいけないのではなく、いかにして、どういうものを、どういう根拠で置くのかが問題なのです。/ 主・客の問題は、日本でもここ20数年に渡って大問題だったのです。〈マルクス主義は真理である。客観的・科学的な世界認識なのだから、それをよく知ることが正しく生きるための道だ。〉そういう考えが大きな力をもっていたのです。だから、主・客問題を十分に考えてちゃんと反省しておくのは大切なことなのです。
鈴木一:
それは分かりましたが、マルクス主義も日本的な精神風土の中に移入されたのですから、基準を立てない・曖昧にしてしまうという〈日本的問題〉が土台にあるはずです。ところが竹田さんの書き方 (『現象学入門』)では、客観や普遍はすべてダメだと読めてしまいます。
竹田:
あなたの言わんとすることはよく分かります。ぼくも、言葉では何も言えないという認識不可能論や、思想、主体の死という現代思想には、大きな異和をもっています。ただそれがうまく書けていないという指摘はありがたく受けとめます。
武田:
理論を考える上で、ひとつ押さえておかなければならないことは、原理的な次元(純粋に学的なもの)と、広い意味での思想(イデオロギー)の次元の区分けです。
もちろん絶対の区分けはできませんが、『現象学入門』は前者なのです。人間や社会についての解釈ではなくて、原理的なレヴェルでの認識の仕組みについて書かれたものです。本当の意味での〈学〉としての哲学であり、いわば数学のようなものです。この次元では経験・実践による検証はできません。言葉の論理として詰めてゆく他はないのです。それに対して、ふつういわれている意味での思想(イデオロ ギー)の場合は、社会的実践の場での不断の検証こそが問題となるわけです。
竹内:
ぼくの場合は、哲学の原理の発想そのものが、はっきりと日本的なメンタリティーとの対決にあるのです。現実の批判にならないような哲学はやってもしょうがない。だから現実との対決ができるような原理を立てる必要があるのです。
竹田:
哲学とは単なる論理ではなく、自分のある切実さから出発しているということについてならば同感です。
武田:
何かしらの疎外感が、追求のエネルギーとなるというのはその通りです。理論に向かう端緒として、この日本的現実をなんとかしたいという思いがあるということには何の問題もありませんが、原理の中に自分の持つイデオロギーを入れるのだとしたらダメです。それは論理としての徹底性に欠けます。また認識論と存在論(解釈)の区分けの問題も極めて重要です。
竹内:
ああ、原理の問題は原理の次元で考えるということについては分かりました。
竹田:
ええ、武田さんの言う通りだと思います。日本的現実から思想への動機を汲んでいるのだが、原理をやるときは、他国の人にも通じるようなものとすべきです。
竹田氏への竹内からの回答Ⅲ P.15 [後述]をご覧下さい。
竹田:
ぼくは、マルクス主義を現象学によって批判してきましたが、現象学だけやっていると、学生のとき考えていた「社会をよくしたい」ということがどこかにいってしまう。だから、たしかに〈自己異化〉は重要なのです。ただ問題は、その契機をどこから得るかという点です。へたをすれば、ただある世代が別の世代に文句を言っているだけということにもなりかねません。ぼくは、被差別者として差別の問題を考えてきましたが、これは大変象徴的な問題だと思います。日本人の朝鮮人への差別は、あまり自覚しないままに行われているために、ふつうの人々はその事を考える動機をもちません。そのときに「差別は歴史的なものであなたたち皆の責任だ。」と言えば、それで終わりになってしまうでしょう。そうではなく、「あなたも生活の中で、例えばチビとかブスとか言われたことがあるでしょう。その問題を一緒に考えてみませんか。」と言えば、多少とも通路が開かれることになります。誰でもみな自分が大事なのです。そこから出発して、自分の狭い殻を、生活の中での挫折に動機づけられて破っていくのです。自己異化が必要だから異化しなさいと言ってもダメです。
竹内:
それはその通りだと思います。
鈴木一:
ただ竹田さんば、塾報33-P.7下にあるように、根本さんの「世界には悲惨がたくさんある。」に対して「・・そうするより他にはない。」と答えています。ここに自分の主観の中に閉じこもるという現象学の影響が出ていると思いますが。
竹田:
何を問題にしているのかよく分かりませんが。
武田:
鈴木君は文脈に沿ってちゃんと読んで下さい。そのすぐ上のところの「(社会問題を解決してゆくにも)変えていこうとする人々の間での妥当をつくりだすことがまず必要となるはずです。」という発言の続きなのですから。変える方法について述べているのであって、悲惨を無視しているのではないのです。
鈴木一:
はい、分かりました。/ また質問ですが、竹内さんは討論についての理念をはっきりと打ち出していますが、竹田さんは日常性を重視するために討論の理念がはっきりしません。
竹田:
生活次元と討論次元を切ることの方に問題があるのです。竹内さんの「我執を去って真理を目がける」という言い方からは、一番正しいもの(ベスト)という印象を受けます。そうではなくて、どう考え行為したらよりよいか(ベター)を話し合うことが大切なのです。至高のものを希求する欲望が人間のなかにあることをぼくも認めますが、しかし何が一番なのかに拘って生きる人は、必ず生活をスポイルすることになります。人間の関係性を狭めたり壊したりするとか。だから、例えば男女の関係性の問題でいえば、熱狂的な恋愛の場面ではなく、現実に一緒に暮らしてゆく中でどうよりよい関係をつくり上げるのかを考えるべきなのです。
竹内:
よりよいということを言うためには、よいという価値基準を設定せざるをえない。
竹田:
論理上は、確かにそうでしよう。
竹内:
それに、夫婦の問題のような例を出すのには危倶を感じる。真理 なんかどうでもよく、仲よくするためにはどうするかという功利的な話し合いになることが多い。人を納得させるにもいろいろある。愛撫によって納得させることもあるが、討論においては説得という方法を使うしかない。そして説得のためには「真理」を基準として立てる必要がある。
武田:
竹内さんのいう「真理」とは〈かけ引きのような話し合い〉に陥らないために必要な「目標」のようなものでしょう。もしそうなら、夫婦間でも「真理」は大いに問題ですよ。どうしたら戦争をなくせるかを考えることと、自分たち夫婦がどうしたらよりよい家庭生活を築いていけるかを考えることは、本質的には同じです。
竹内:
いや、夫(妻)とは何か?を考えるのならば真理追求になるが、功利的な話し合いにしかならないことが多い。それに愛撫で解決することもある。
武田:
それは、竹内さんの夫婦観がおかしいのです。当然いろいろな次元があるが、いま竹田さんの言っている夫婦間の話し合いとは、どうしたらよりよいかを考える次元についてですよ。
竹田:
もし、日常世界のレヴェルと討論のレヴェルを切るとすれば、結局は〈理論を持っている人間が決める〉ということになってしまいます。どんなに世界的な問題でも、それを自分の頭でちゃんと考えるときには、その根拠は自分の生活の中にあるのです。それ以外のどこからも持ってくることはできません。なぜ竹内さんは二つを切る必要をいうのですか?
竹内:
切るというのではなく、具体的経験を相対化する契機は、討論という純化された真理追求の中にあるということです。人間のコミュニケーションにはいろいろあるが、何がドミナントになるかを考えることです。夫婦の場合だったら愛撫がドミナントになることが多いが、 戦争の問題を考えるときには討論による真理追求がドミナントになるわけです。
竹田:
いまの話は全く説得力をもちません。竹内さんは、一体どこからどんな方法で「真理」や「普遍性」を導こうとしているのですか? 自分の家庭生活をよりよいものにしたり、身の回りの問題を解決したりすることの中に、唯一、社会問題を正しく考え、普遍的なものたらしめる方法や根拠があるのです。どんなに理論的な話のときでも、頼りにするもの(基準)は、生活の中での「これはよいごとだな」というおもいなのです。
竹内:
具体的経験を絶対化する傾向が現象学にはあります。それを相対化するためには討論が必要なのです。何がドミナントになるかを考えることです。
竹田:
そんなことを聞いているのではありません。「真理」を根拠づけるものは何なんですか?
納冨:
竹内さんば、真理は遥か彼方の北極星のごとくだと言っているようです。そしてその方向を目指して討論をしてゆくことが真理だというのでしよう。それに対して、生活の中で実際に私たちが「何が正しいか」を考えて一応の結論を得る。それがそのつどの「真理」だとすれば、それ以上の何か形而上的な真理は必要ないというのが竹田さんの主張だと思いました。/ 私は労働組合の運動もしていますが、従来のように集団をマスとして捉えて全体を動かすにはどうするかを考えるのではなく、本当に一人ひとりに動いてもらうにはどんな言葉(思考)が必要なのかを考えたいと思っています。そのへんが「現象学の意義」だと感じます。
竹田:
ええ、そうだと思います。竹内さんに重ねて聞きますが、真理性を追求するという「討論」と「日常の生活」の二項の関係はどうとらえるのですか。
竹内:
具体的経験の挫折によって具体的経験を捉え直すことになるわけだが、その挫折を克服するのにはいろいろな方法がある。例えば夫婦間では愛撫によって克服することもある。真理性を追求する討論もその方法の一つだ。討論をできるだけ純化させてやってみる。その中で自己鍛練することが日本社会においてはとりわけ重要である。
武田:
討論(塾)という二次的な場で得られた自己鍛練の成果は、夫婦間を含む日常の生活に役立つはずです。
竹内:
夫婦は他の方法で結びつくこともできる。真理性を媒介にしないのはよくない夫婦だとは思わない。生活に役立つなら結構だが、別に役立たなくてもかまわない。
武田:
何かしらの形で現実生活にプラスになって始めて二次的な場での討論というものに価値=意味は生じるのです。そうでないないなら一体何の意味があるのですか。
竹田:
その通りだと思います。ぼくも討論の重要性をはっきりと認めているから、こうして討論会に参加しているのですが、さっきから何度も聞いているのは、具体的な経験=生活の中で「真理」が根拠づけられないのならば、どこで根拠づけられるのかということです。
竹内:
それは、具体的経験の挫折によるわけです。・・・
竹田:
そんなことを聞いているのではありません。
阿見:
竹内さん、ケーススタディーをやってみて下さい。みなが談笑しているところに、一強盗が入ってきたとします。強盗が去った後、警察がみなに犯人の特徴を聞きます。しかし一人ひとりの言うことが一致しません。居合わせた人が話し合う(討論する)のですが、なかなかまとまりません。こういう時にどうしたらよいかです。
竹内:
それは、お互いが真理性の前で謙虚にならなければダメです。
阿見:
もちろん理念としてはその通りですが、問題は、具体的な経験の場でどのようにしたらその理念(我執を去る)の方向に踏み出せるか?を考えることではないですか。「我執を去れ」「自己異化が必要だ」と言ってみてもどうにもならないはずです。具体に即してその方法を考えてゆくのが本当の哲学なのであって、理念を繰り返し言ってみても何の役にも立たないと思います。
竹内:
それも分かりますが、純化した討論がやはり必要なのです。
竹田:
純化した討論が必要ないなどとは言っていません。ぼくは、ふつうに生活している人間が我執を去った討論を始めることの根拠はどこにあるのかを聞いているのです。それを明確に言わなければ哲学ではありません。
竹内:
真理性を追求して問題を解決しようとする意志が生じた時に、いやでも我執を去るということが出てくるのです。いやらしいと感じる人間の言ったことでも、「正しいな」と思ったら従うことになるわけです。真理性追求の意志があると我執を去ることにエロスを感じるようになってゆくのです。そういう討論が日本人に一番欠けているのですから。
皆川:
家庭というと始めに社会通念上の枠があります。差異を際だたせる「討論塾」でのような討論は日常の場ではなかなかできません。そこにこの塾の存在意義があると思います。
鈴木一:
今の思想界の状況を見たとき、純粋化させた討論によって真理性を見い出していこうというのはとても重要なことだと思います。
竹田:
それが必要なことはぼくも十分に認めていますが、しかし今一番やらなければならないのは、ふつうの人々が〈こうやって考えれば、世の中をよくしてゆける可能性があるんだ〉という根拠をはっきりとした形で示すことだと思います。 竹内さんのいう日本的なものうんぬんというのは、ぼくもそうだとは思いますが、そればかり繰り返されるとイヤな感じがします。みなが本当に変わってゆくためには、そんな言い方ではなく、「ほんとう」を見い出す希望をどう作り出すかを生活に即して語ることだと思います。
武田:
竹田さんは、討論塾のような会をつくって討論することの価値を十分認めているのです。ただそれが自分の取り組むべき最重要な課題ではないと言っているだけです。
竹内:
ああ、よく分かりました。
石曽根:
私は、「夫婦間の問題は愛撫でも解決することができる。」という竹内さんの発言、その根底にあるニュアンスにいやなものを感じました。いま若い夫婦の解体がどんどん進んでいます。そういう場でこそ、幸福とは?家庭とは?について話し合うことが必要でしょう。「討論とは何のためにするのか」を考えることは、こうした現実の問題をもっとよく知って、そこから始めなくてはいけないと思います。身の回りの人たちとの対話によって、真理=ほんとうの追求をすることが 一番大切ではないでしょうか。哲学をするためには、生活者の感覚を持つことが必要だと思います。竹内さんの話は、観念的で固定した言葉の繰り返しでしかなく、心に迫ってくるものがありません。それが何故なのかをよく考えてみることが、大きな課題ではないでしょうか。
佐野:
特別な場所をつくって「考える」ことにも、もちろん意味はあるで しょう。ただそれ以上に大切なことは、日々、切実な問題を突きつけられる〈家庭〉や〈地域〉や〈職場〉の中で、何が本当なのかを考えたり語り合ったりすることではないですか。もしそれをしないなら(二次的な)討論会には何の意味もありません。/ また、なにをするにも楽しいとか明るいということは大切ですね。いつも竹田さんの話からは生き生きとしたものを感じます・日本人に一番欠けているのは、そういう一人ひとりの輝きとか自由ではないかと、思いますよ。
武田:
では、このへんで終わりにしましょう。食事にしたいと思いますので、隣室にどうぞ。ワインは佐野さんのおごりですので、遠慮なくやってください(笑)。
【文責・武田康弘】
竹田氏への竹内からの回答(Ⅰ)
A
始めに----
①今日のthemaは竹田氏の問題提起〔塾報33-P.15〕中のB1・2・3・4への回答。つまりは現象学をめぐる討論。 ②ただし、竹田氏がここで「現象学」と言っているのは、明らかにHusserlの現象学だけと思われるので、そのように限定。 ③関連文献は私に関する限り、『具体的経験の哲学』の第二論文でなく第一論文。
B
問題提起B1・2への回答
竹田氏の質問は、1.現象学が「絶対的真理」の基礎付けという「目標」をもっている、ということについて。 2.現象学が「ロゴス中心主義」である理由について。
Husserl現象学がa prioriな絶対的真理の追求の構えをもっており、且つlogos中心主義的であることは、私にはまず疑えないようにみえる。その理由----
①最初期の『現象学の理念』で早くも彼は「現象学」をDescartes の懐疑→cogitoの絶対的明証性からKantの認識批判の学に至る〈超越論的観念論〉の系譜を継承するものとして位置づけ、現象学的研究分野の特徴を、「純粋明証性の領域」「絶対的自己所与性内部のa priori」「絶対的認識の分野」と呼び、その使命を「あらゆる(学)知の絶対に確実な地盤を獲得すること」としている。
②主著Ideen Ⅰの記述仕方を見ても、絶対知を追求 したDescartesのcogitoが現象学成立に決定的役割を果していることは明らかで、『Descartes的省察』でもこれを明言、己の現象学を Neu-Cartesianismusと規定している。「われわれは学問を絶対的に基礎づけるという目標を決して放棄しない」というわけ。
③『厳密学としての哲学』でも、Diltheyの「世界観としての哲学」の歴史主義・相対主義を峻拒し、極めて理性主義的・絶対主義的な哲学の理念を呈示している。
④なるほど、晩年の『危機』においては、彼はLebenswelt(生の世界)を哲学的思索の基準に据えることで、如上の理性主義的・絶対主義的な知の性格を脱ぎ棄てたかにみえるが、しかし完全にそうしたわけでなく、そこにはかなり深刻な狐疑逡巡や内的矛盾の見られることを指摘したのが私の text P.21の文章で、ここを理解していただくには、Merleau-Ponty『知覚の現象学』(みすず)P.237や新田義弘『現象学とは何か』P.145などを参照 下さい。textとなるのは『経験と判断』。
⑤また『危機』段階でも彼がヨー ロッパ中心主義の合理主義的観念論の枠に囚われたままだったことについては、『思想』誌83年5月号の山崎カヲル論文を読まれたい。
⑥また彼の言語論における1ogos中心主義的性格については、私のtext P.60-2を参照下さい。
以上のHusserl現象学観は、私だけでなく、P.Ricoeurをはじめとする大多数のHusserl研究家の大筋で一致した見解だと思うが、しかしここで重要なことは、Husserl現象学をめぐる私の見解と竹田氏の見解との何れが正しいかを争うことではなく(そんなことは学会とか研究会とかで実際に Husserlのtextを前にしてすればよい)、むしろ、そこから出発して私が形成した私独自の現象学観を氏はどう判断するか?私と氏それぞれの独自の現象学観の異同はどこにあるか?今それを明確化することだ。そこで以下、私自身の現象学観を、それもまず始めには〈真理〉問題をめぐる部分だけに限定して述べよう----
問題の焦点は、cogito=純粋意識=具体的経験の地平に〈真理性〉や〈明証性〉の証しを求めてきたDescartes以来の伝統ときっぱりと訣別し、その地平に全く新しい〈実存的〉意義を付与すること。私のtext P.22の Mer1eau-Pontyの言葉『真理と誤謬との手前にあって、その何れをも可能にするもの』→P.24『真理が真理としての意味をもつ場、したがってまた逆に誤謬が誤謬としての意味をもつ場、しかもその究極の場』→P.25の Ricoeurの表現「存在論的優位性と認識論的劣位性のparadoxe」を参照さ れたい。その限りでは、Vicoの次のDescartes批判は正しかった(現代日本におけるVico悪用は別にして)「cogitoの確実性は意識conscientiaの確実性であって、知scientiaの確実性ではない」。
では、なぜcogitoに知の確実性が求められぬのか?根本的には、cogito =意識の「自己への現前」は、同時に「自己脱出」でしかない〔text P.22-3〕 からだが、さらに、これを顕在知にまでもたらす「現象学的還元」=「浄化的反省」の操作が「極めて困難」「完全には不可能」だからである〔同P.23〕。もっとも、私も『サルトル哲学序説』の序章「現象学的存在論の形成」を書いていた=時代には、対象の「何」を把える「超越的知覚」(「射映」を通じた不十全な知)と対立する、対象の「如何に」(対象の存在仕方=意識の指向仕方)を把える「内在的知覚」の確実性・十全性を信じていた〔同書P.16-27〕。 だが、「還元」の不完全さを知った今ではこの確信もゆらぎ、cogitoや具体的経験の場に〈真理性〉の証しを求めることは一切禁欲することにした。なお、このことは言語論的考察からも言えることで、これについては、text P.108-9を参照されたい。
〔竹内〕
(注)フッサール哲学の変遷ということに関しては、次に上げるレヴィナスの見方が正しいと、私(武田)には思われる。
「たしかに超越論的観念論は、『論理学研究』ではまだ自らを意識していないし、多くのテキストはこの解釈に対立するようにさえ見える。『論理学研究』から『イデーン』への発展があったということをわれわれは否定しない。・・しかし、この発展はとりわけ、フッサールにとって、『論理学研究』で述べたテーゼが要求することすべてを自覚し、明示化することに存したのである。 ・・フッサールの探求の漸次的歩みは一種の上昇であり、その上昇過程においては発見された各々のことが、上昇に応じて、より完全な全体の中に、より広い地平の中に、位置づけられるのである。」
(ウニベルシタス357:『フッサール現象学の直観理論』P.146)
竹田氏への竹内からの回答(Ⅱ)
C
問題提起B3への回答
竹田氏の質問は3.現象学における主観性(自我)の重視を、なぜ、どのように乗り越える必要があるのか。
私は現象学の発掘した純粋意識=具体的経験から〈真理性〉の根拠を消去すると同時に、また〈自我〉をもそこから追放すべきだと考えている。つまり、竹田氏のように「Husserlの方法的独我論」なるものに追随する必要はないと考えている。その理由----
まず、近代的自我主義からいかにして脱却するかが、現代哲学にひとしく課せられた、逃すべからざる課題であり、現象学もこの課題を果たすべく、Husserl以後それなりに多くの努力が重ねられてきている。事実、『Descartes的省察』におけるHusserlのEinfühlung(自己投入)による他我構成論は、まず自我認識の直接的明証性を前提とし、そこから出発して他我をその自我による構成的対象とみなすもので、木田元氏のように、「こんな他我は、マネキンに投影された自我でしかなく、全く他我ではない」とまで言うのは酷評かもしれぬが、とにかくひどく説得力を欠くものだった。
この点、初期Sartreの『自我の超越』や「Husserl現象学の根本理念」に見られる、「超越論的意識」から自我を追放し、自我を少しも特権化しない考え方は、戦後に生きる私には極めて鮮烈なものにみえた。また、『存 と無』における、自我の受動化、対象化の体験を通じて主体としての他者の存在を確認するという他者論の方が、Husserlの「自己投入」による他者構成論よりもはるかに説得力あるものに映じた。現代における個別諸科学の成果 ----例えばH.Wallonの発達心理学やG.H.Mead以来のsymbolic相互作用論などの成果を踏まえて考えても、この方がより斉合的だろう。またRicoeurも認めているように、Marx主義から来たideology批判とFreud 以来の精神分析の営為をこれに加重してくれば、自我の内省的認識なぞ、他我の客観的認識にもましてあやふやで当てにならぬことが、誰の目にも明らかとなってくるだろう。
要するに、自我とは他我と等しく世界のなかの外的な一実体でしかなく、各人の具体的経験にとって何の特権ももたず、この点に関する限り、「個人あって経験あるに非ず、経験あって個人があるのである」と言う西田幾多郎の言は、DescartesやHusserlよりも正しいと思う。またM.Buberが「す べての真の生は出会いである」と言うのも正しく、まことに〈具体的経験〉とは、そこで自分が他者とも自我とも出会い、共存をも孤独を斉しく経験する、純粋な〈出会い〉の地平だと思う〔text P.17,19〕。
〔竹内〕
竹田氏への竹内からの回答(Ⅲ)
D
問題提起B4への回答
竹田氏の質問は、4.現象学の根本的な意義について。
以上のように、私はHusserlの現象学から、その真理性の根拠としての性格と自我主義的性格とのニつを除去した上、更に最晩年の彼のmetabasisの思想を拡大発展させて、具体的経験それ自体の〈自己=異化〉の作業をも可能にしようとするものだ。text P.25,27-8を参照。だが、なぜそうするのか?その理由 ----
私もまた竹田氏の感じている、外なる客観的状況から出発 して自己を規定してゆこうとする旧Marx主義への強い反発は、実によく解るし、全く同感だ。しかし同時に、現代日本の、特に若者たちに多く見られる自閉的なme-ismなるものも実に困ったものだと思っており、これではますます世界から日本人は軽蔑されるばかりだと感じている。そこで、少なくとも思想次元で何とか両者をのり超えられるようにと、あくまで具体的経験から出発しつつも、それが自らの力で自らを〈異化する〉----そうした道をつけようとした次第。多分、ここは氏とかなり大きく対立する点かもしれない。
以上三つの修正点を付加した上で、私は現象学が発掘した〈具体的経験〉の思想をどこまでも継承するものであり、そのことの現代的意義は、text P.29以下で三つにまとめて呈示しておいた通りだ(追加的には更にP.39以下のArthusser派批判、P.42以下のLevi-Strauss批判をも参照)。これらの点について、竹田氏の方からのご感想を伺いたい。
〔竹内〕
以下は、『自分を知るための哲学入門』竹田青嗣著(筑摩書房)よりの要約 - 抜粋です。文責は、武田。
「個人の中の内的な信念、「正しさ」は、それ自体として生き延ばされても何の意味も持たない。それは、具体的な人間関係の中でつねにその妥当を試されるときにだけ、またそういう努力の中でだけ、はじめて意味を持つ。そのように現象学は教えるのである。なんらかの真理(=信念)によってひとびとや現実を判断-裁定するのではなく、自分の信念の方をひとびとや現実によって試すこと。このプロセスにおいてのみ、人間の脳裡に棲みついている「正しさ」は《独我論》を抜け出すことができるのである。あらかじめそれ自体として保証された「正しさ」などどこにもないからだ。‐‐現象学のこういう視線は、思想というものの本来的な意味合いをも、はっきりと解き明かしている。思想とは、自分の正しい「立場」を打ちたてるものでも、隠された奥深く高尚な「真理」を告げるものでもない。思想とは、立場の違った人間どうしが、生の意識のヒューマンな核(欲望)に訴えて、互いの信念を編み変え、新しい了解の通路をつけるような新しい言葉をつなごうとする営みである。‐‐思想の本性とはそういうものだ。」