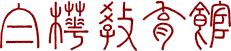�@ �u���_�̓N�w�v����u�̌��̓N�w�v�ւ̐[���̂��߂ɁB
137.�@�s���̒m��b����
�@�@�@�@- �|���N�w�Ɩ��v�z���z���� -
�@�^�P�Z���i���c�N�O�j�����N�ɂ킽��^���Ɏ~�߂���ŁA���ݓI�ɔᔻ�����z�������{���\�����l�̓N�w�� �]�|���F�Y�������@�x�i��Ȃ��ނ˂悵�j�] �Ɋւ���u���O���ȉ��ɏЉ�܂��B
�@�Q�P���I�̍����A�������S�́u���_�̓N�w�v����A�������E����ՂƂ����u�̌��̓N�w�v�ւƕ���i�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ�������܂��B
�@��ꂽ�����̃R�����g�����̂܂܌f�ڂ��܂��B���ӌ��E�����z�����҂����܂��B
�|���N�w�Ɩ��v�z�̂킽���̌���
�@�@�@�@�u���_�̓N�w�v����u�̌��̓N�w�v�ւ̐[���̂��߂ɁB
�|���N�w�Ɩ��v�z�ւ̂킽���̌���
�@���Ă킽���́A�T���g���A�������[���|���e�B��̖|���+����҂ŁA�Ǝ��̎v�z�����N�w�҂̒|���F�Y����Ɏt�����A�[���𗬂������܂����B�Q�O�N�ȏ� �O�̂��Ƃł����A�|������̑S�����ǂ݁A��v�ȓN�w��i�̃��W�������쐬���A�w���_�m�x�̗����グ���ɂ͂��̒��S�҂ƂȂ�܂����B
�܂��A�w�������w���x�i�� ��������ɂ���u�N�w������v�̔M�S�ȎQ���҂ł���������͂��������o���A�킽�����S�R���Z�v�g���쐬���đn�݁A���͉䑷�q�s���^�c�j������Ƃ��� �W���I�Ɏ��g�̂��A���@�x�̎v�z�ł��B�P�O�N�ȏ�O�̂��Ƃł����A���@�x�S�W���w�����A�ߌ��r�コ��␅����C�u�����̉���A�����j�q����́w�����q�`�x�A�܂��ŋ߂ł͒����^������́w���@�x�x�ɂ��w�тȂ���A���̎v�z�̊j�S��T��w�͂����Ă��܂����B
�킽���́A�ނ�̌��v�z�Ɋ��S���Ă悫���̂܂������A�����Ɉ٘a���o���܂����B�[�I�Ɍ����A�ނ�̎v�z�́A�C�f�I���M�[�̎����ɂ�����u�D�G���v�ȏ�̂��̂��������A�����ɐ�����킽���̐S�g�ɂ܂ł͓͂��Ȃ��A����ȕ��Ɏv�����̂ł��B
���|�^�����x������H�I�Ȗ��@�x�̎v�z�\���ϗ͂ɗD�ꂽ�ނ̓N�w�v�z�Ƃ����ǂ��A�ϔO���������A�r�r�b�g�Ȍ������o���牓���A�^�̃��A���e�B�������Ȃ��̂ł��B
����ɐ�����|���F�Y����̎v�z���A�u��̓I�o���v�̓N�w��搂��A�������ɉ������邱�Ƃ������ӎ����Ȃ���A��͂肻�̖������͌��ꐢ�E�ɗ��܂�A�L����������܂���B�ł��_���Ɏx�z����A���X�����������x����L�����A�����A�_��Ƃ͉����̂ł��B
����l�͎����������قȂ�܂����A�]�_�ƂƂ��Ă̎v�z�Ƃ��w���̓N�w���t�Ƃ͂܂�������r�ɂȂ�ʂقǗD�ꂽ�v�z��W�J���܂����B�������A�킽���͂� ���ɏ����������ɉ��l��u���N�w�̌��E�������Ă����̂ł��B�ނ�̓C�}�W�l�[�V�����̍L��Ȑ��E�ɒ��ڂ��Ȃ�������ǂ͌��ꒆ�S��`����E�p�ł����A�u�� �_�v�Ƃ��Ă̓N�w���D�悵�A�u�̌��v�Ƃ��Ă̓N�w�͒��r���[�ɏI���܂����B���̌������킽���́A���炪���̓N�w�̊j�Ƃ����T�O�ɑ��āy�s�O��z�ł��� ���炾�ƌ��Ă��܂��B���̂��߂Ɂu�N�w�̌����v�̒Ƃ͂Ȃ炸�A�u�C�f�I���M�[�Ƃ��Ă̎v�z�v�̎����ɗ��܂炴��Ȃ������̂ł��B
�|���F�Y����̓N�w
�|���F�Y����́A���g�̓N�w�̕��@�I���u�Ƃ��āu��̓I�o���v���f���Ă��܂������A����́A��̃u���O�ɋL�����ʂ�A�Ԑڌo���ƒ��ڌo���Ƃ̈Ⴂ�ɖ����o �Ȍo���T�O�ł����B�u��̓I�o���v�Ƃ́A�����܂ł��u�}���N�X��`�Ƃ����ɂ߂ċq�ώ�`�I�ȗ��_�̌n�Ɛ茋�ԁv�i��g���X���w��̓I�o���̓N�w�x�̂͂��߂ɂ����j���߂̕��@���Ƃ���A�N�w�̌����ł͂���܂���ł����B
�u��̓I�o���v�́A�킽���̂悤�ɒ��ڌo���ɂ܂ŊҌ����邱�ƂœN�w�̌����ɂȂ肤��̂ł����A�Ҍ����s�\���ȈׂɁu�����v�Ƃ͂Ȃ炸�A�u���_������ ���邽�߂̑��u�v�Ƃ��Ĉʒu�Â����܂����B���̕s�O�ꂳ���A�|������̓N�w����v�z�i�C�f�I���M�[�j�̎����ɗ��߂邱�ƂɂȂ��Ă��܂����ƌ����܂��B
�u���͎�����Ȃ��Ă��{�����_�����㐢�Ɏc��v�A�Ƃ����|������̌������́A�u�������錻�݁v�ȏ�̉��l�𗝘_�ɗ^������̂ł����A���ꂪ�A�� �팾��Ƃ͈قȂ�����i���_�j�Ƃ��Ă̋���������ڂ�����w�͂ƂȂ�܂����B���̎p������u�m���l�Ƒ�O�v�Ƃ��u��w�l�ƈ�ʐl�v�Ƃ����@���� ���A���҂̕s�f�̌𗬂��߂����ׂ��Ƃ����咣���o�Ă��܂����A���������@�͌���ł̓��A���e�B�������Ɠ����ɁA��낱�т��L���鐶�����▯������̎� ������邽�߂ɂ̓v���X�ɂȂ�܂���B
�킽���́A�l�Ԃ̑Γ����i���R�ƕ����j����ՂƂ��閯��I�ȗϗ��v�z���Ȃ���A�N�w�i�P���ɓ����l�Ԃ̐��j�́u�����v�����Ă��A�����̃C�f�I���M�[�� �ׂ�ƍl���Ă��܂����A����ł͎ア�v�z�ɂ����Ȃ炸�A�l�Ԃ̐��̌������P�����A�x����͂������܂���B�킽������̓I�o���ڌo���ɂ܂ŊҌ�����N�w �����̂́A�N�w�������ɂ����炷���߂Ȃ̂ł��B
�w�̌��i���ؐ��j����o������N�w�\�\�u��̓I�o���̓N�w�v�ᔻ�U�\�\�x�����Ђ������������B
�킽���ɂ́A�T���g���̉߂��i���g�̎�����`�Ƃ����v�z���A�}���N�X��`����������I���_�ƋK�肵�Ă��܂����j��|������͌�ǂ����Ă���悤�� �v���܂��B��̓I�o���Ƃ����M�d�ȊT�O���A�u���_���������邽�߂̑��u�v�ɂ����̂ł́A��̓I�o���i�������Ă��鍡�̌o���j�͌��������Ă��܂��� ���B�T���g�����|�����������̒��S�e�[�[�ɕs�O��ł��邪�䂦�ɁA���X�́u�̌��v���P�����u���v�̓N�w�ɂ܂Ői�ނ��Ƃ��o�����A�m���l�̗D�z�Ƃ������� �ɗ��܂����̂ł��B������������������A���ɏq�ׂ���@�x�̎v�z�Ƌ��ɔނ�̓N�w�́A�������E�ւ́u�R�C�f�I���M�[�v�Ƃ��Ă̖������ʂ����݂̂ŁA �u���v�̐����x����u�N�w�̌����v�ɂ܂Ő[�܂邱�Ƃ��Ȃ������ƌ����܂��B
���@�x�̎v�z
�ł́A���ɖ��@�x�ɂ��Ăł��B
���́A�N�w�k�i����N�w�ȁj�Ƃ��Ă̏o���̑O�A�w�K�@�̒����Ȃ̂��납��w���ȐM���x���̃G�}�\���̒���ɐe����ł������n�̎�҂ł����B�Q�P�œ��l�� �w�����x�̑n���ɎQ�����A�����^���ɂ�����u�N�w�Ǝv�z�̒��S�ҁv�ƂȂ�܂����B�ނ́A���y�Ƃ̌��q�i���˂��j�ƌ������Ă��������̉��[���ܘY�̊��߂ʼn� ���q�Ɉڂ�Z�ނƁA�u�꒼�ƁA���ҏ��H���āA�o�[�i�[�h�E���[�`���W�߁A�䑷�q�𔒊��h�̋��_�Ƃ����̂ł��B
���̎v�z�̌��_�́A�Q�S�̂Ƃ��Ɂw�����x�ɍڂ����_���ɖ��Ăł��B
�u���Ȃ������ēN�w�ɂ͈�̏o�����Ȃ��B�E�E���Ȃ𗣂ꎩ�Ȃ̗v���������āA�N�w�͉���̗͂������炳�Ȃ��B��������ꐫ��r������q�ϓI�ԓx�͋�����Ȃ��B���͓N�w�ɂƂ��ĉi���ɐ₦�邱�Ƃ̂Ȃ��_�O�̓��ł���B�v
�����g�̐������ɂ��Č���A���̌�̗l�X�Ȋ����ɂ��ω��̒��ł��A���̌��_�݊O�����Ƃ͂Ȃ������ƌ����܂��B�ނ́A�O�Ȃ�v�z�̌n�ł͂Ȃ��A�� ����̏Փ������������d�A��������g�̌����Ƃ��A���H�I�v�z�ƂƂ��āu���|�v�^���𒆐S�ɗl�X�Ȋ������s���܂����B�������A���̎v�z�����̂͒m�� �l�Ƃ��Ă̔ނ݂̂ł����B
���|�^���ɂ�����m���l�ƍH�l�ɂ��ẮA�D�ꂽ�m���l�ɂ��H�l�̎w���Ƃ��������ŁA�H�l�ƌl��Ɓi�m���l�j��Η���������ŁA�݂��̊w�э����� �咣�����ɉ߂��܂���i�u���O�͕������͂Ȃ����A���S�œĐM�ł���B������m���l�́A�������͂��邪�A���S�ɂȂ肫��Ȃ��v�j�B�܂��A�Љ�ϊv�̖��� ���A���O���]���ŎI�ȑ��݂ƈʒu�Â��A��̓I�ȑ��݂Ƃ͂����A���O���g���N�w�ҁi�N�w����ҁj�E�Љ�I���H�҂ƂȂ��Ă������Ƃɂ͔ے�I�ł����B
���E�����������g�̓N�w�̌����Ƃ��Ă��������A�Ȃ��m���l�ȊO�̖��O�̌��E��������ے肵�Ă��܂����̂��H�@
���̃G���[�g��`�������炵���̂́A�y������A�Ƃ��������̕s�O��z�ɂ���Ǝv���܂��B���̕s�O��䂦�ɁA���|�^���́A�����`�Ƃ͉����[�֎�`�ɗ��܂� �܂����B����́y���z����i�̌������ρj�Ƃ������W���O��l�ЂƂ�̂��̂Ƃ���N�w���������邱�ƂɎ��s�����̂́A�������m�Ƃ͈قȂ���{�����̓� ���������o�������Ƃ��������~���������Ă�������ł��B
���{�����̓Ǝ������y�����z�Ƃ������_�́A������A�Ƃ��������ƏՓ˂��܂��B��l�ЂƂ�̂���̂܂܂̑��ݎd���ɂ��̂ł͂Ȃ��A�O�Ȃ������z���i���̏ꍇ�A�����Ƃ������_�j���猩��Ƃ����̂́A������̓N�w�ł͂Ȃ��A�O�Ȃ�@���I�v�z�Ɋׂ�܂��B
��ʂɁA�����A���ƁA���i�V�c�j�A�_�A���ҁA���_�E�E�E�E�Ȃ�炩�́y���z���z��u���A�������玩���␢�E���݂�Ƃ����v�z�́A��̃C�f�I���M�[����`���@���Ɋׂ�A�u���v�̑��݂���o�����A����̑̌��̖��ؐ��������Ƃ���N�w�Ƃ͂Ȃ�܂���B
���́A�������u�q�ώ�`�v��ے肵�A�u��ϐ��̒m�v�ɂ��N�w��錾���Ȃ�����A���g�Ɩ��O�́u���v����̌����ɓO�ꂷ�邱�Ƃ��ł��Ȃ������䂦�ɁA���܂��܂ȊO�Ȃ��i�����A�_�A�n�����E�E�Ƃ������z���j��������Ȃ��Ȃ����̂ł��B
�l�ԑ��݂̑Γ����Ƃ�������I�ϗ��ɂ��A��l�ЂƂ�̑��݂�����Ύ҂�F�߂��A�e�������W���ƂȂ�Ƃ���������̓N�w�̌�����O�ꂷ��A�u���z ���v��u���Ƃ����ア�v�z������I�v�l���G���[�g��`�����z�N�w�Ƃ������̂́A�m���l�𒆐S�Ƃ����l�Ԃ̕s����������e�ł����Ȃ����Ƃ�������� ���B�����琶����A�Ƃ������m�i�N�w�j�̐��́A���_�ł͂Ȃ����X�̎��H�ł��邱�Ƃ������ł���A���p�ȗ��A�̎R�͏����A�������߂��u�ӂ��v�i���N�ȃG �l���M�[�Ɉ�ꂽ���A������ɂ��鐶�A���S�E���R�Ȑ��j������Ă���͂��ł��B
�~���������A
���_�ƂƂ��N�w�҂ƌĂ��l���������{��ǂ݁A����𗧋r�_�ɂ��Ď����̐l����Љ�̂���悤���l����Ƃ����t��������������Ȃ���A�u���v�����W ���Ƃ��鎩�����g�̐l���͎n�܂�Ȃ��͂��ł��B�ق�炢�A�����̗ǔۂ⑼�҂̌����́u���v�̓��X�̐������E�̌o�����犴���E�v���E�l���邱�Ƃ���ɕ]���� �ׂ����ƂȂ̂ł����A�ǂ��������͂Ȃ��Ă��܂���B
�ǂ̂悤�ȏ����ł���A�����̎v�z����ɂȂ��āu���v�̐������E�𗥂���̂ł͋t�����Ȃ̂ł����A�u��ϐ��̒m�v�̈琬���Ȃ��w�Z����̂��߂ɁA�l���� �Љ�̂���悤�܂Ō��Ў҂���������������Ǝv�����܂���Ă��܂��B���������ƂɁA�܂��܂��u�N�w���_�̐^���v�ɏ]���I�H�Ƃ����t���������z�O���Y���Ă� �܂��B�N�w���u�����n�[�o�[�h��̐搶���̂��v�ł́A�u���v����͂��܂�D�ꂽ���͉i�v�Ɏn�܂�܂��A����I�ϗ����������܂���B
���z����u�����A������́A�Ƃ����y ���X�̑̌��̏Ȏ@�Ɋ�Â����ؐ��̓N�w�z�������Ƃ���l������݂����A�킽���͂����v���A�������Ă��܂��B�������A�N�w�Ƃ́A�m���̊l���◝�_�̍\�z�ł͂Ȃ��A�[���[����ڂ����悭�����悤�Ɨ~���邱�Ɓ����H�Ȃ̂ł�����B
�P�P���R���̃u���O�[�[�u���v����ł͂Ȃ��u�O�v��旧�Ă�--���{�̍�����������Ђ������������i����́A�j�S���̊j�S�ł��j�B
���c�N�O
�^�P�Z���́w�v���̓��L�x���@2011-11-25
�ȉ��̓R�����g���ł��B
�f�G�ł��B�e�a�̋����ɂ��ʂ��܂��B (�������q)
2011-12-01 10:58:35
���c�搶�̐c�͂܂��܂���������Ƒ����Ȃ��đf�G�ł��B���N�Ɍb�܂�ĉ��̐l�����̐������������ĉ������I�W�O���߂������������ċ��邱�Ƃ���ɂ����B�ǂ�������ΑP�����l���Ă䂫�܂��B
�����������A���̂������A�^�������߂�[�����Ƃ������Ă�������Ȃ̂ł����A �u�̌��o������̓N�w�v�Ɛ搶�����������ƁA�l���邱�Ƃɗ͂��o�܂��B
�N���Ƃ�Ȃ���c�t�ł����A��������邱�Ƃɂ��Ă����܂��B
�g�т��Ɨ����Ńq�h���Ȃ�܂��� �����lj������B����
�厖�Ȏ��������܂��� �w�������� �m���l�ł��鎖����Ȃ��B���m�̓N�w�͕����̐e�a�̏C�s������w�����Ȃ��Ă��~���� �����ɂ��ʂ��܂��ˁB����
------------------------------------------------
���ӂł��B (���c�N�O)
2011-12-01 11:56:41
����������݂ɂȂ�R�����g�A�ƂĂ����ӂł��B
�������A�e�a���@�����E�Ő����������Ƃ�N�w���E�i������̂悫�������̒Nj��j�ŏo����A���{�����A�ېl�ނ̕������ς��܂��ˁB
�O�ł͂Ȃ��A������A�����I�ɁA�̍l�����E�������́A�K���Ɛ��E���a�����ʂ���͂��ł��B
------------------------------------------------
�o�F�ł��B�т����肵�܂��B (���c��u)
2011-12-02 20:52:54
���̃u���O�[���E�|���ᔻ���畐�c�N�w�̓W�J�́A���ɏo�F�ł��B
���́A�������|������ɁA�搶�قnj������ᔻ�͎����Ă��܂��B
�悭�悭�l���Ă݂܂��B
�搶�̓��̓I�����āA�v�z�I�̗͂ɂ́A�т����肵�܂��B
------------------------------------------------
���_�Ƃ��Ă̓N�w�ł͂Ȃ��B (���c�N�O)
2011-12-03 13:42:49
���c���������ȃR�����g�A���肪�Ƃ��B
�킽���́A�t�ł������|���F�Y���瑽���܂������A���̋Ɛт������]�����Ă��܂��B
�܂��A���@�x�̎�X�̎d�����ƂĂ��L�Ӌ`�Ȃ��̂ƌ��Ă��܂��B
�킽���̔ᔻ�́A�N�w���u���_�v�i�����j�̎����ő�����n�����邽�߂̂��̂ł��B��l�ЂƂ�̐������E�́u�̌��v�Ɏx����ꂽ���ؐ��̐��E��L�Ӌ`�Ȃ��̂Ƃ��邽�߂ɁA�ނ�̌��E���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��A�Ǝv���̂ł��B
���ւ̐��_�ɂ�鏅�@��`�Ɏ����Ă͐l�Ԑ��_�͎���ł��܂��܂����A
���_����Ɏ����ĉ��Ή����Ă����I���ł��B���̓�̍d�����玩�R�ɂȂ�A�P���A�L�т₩���A�x�сA�_��A�s���E�E�E�̐��̂��߂ɂ́A�]���̌��ꒆ�S ��`�̓N�w�ł͂Ȃ��A�ӂ��̐l�̐������E����n�܂�A�����L�`��������u������̐��v���x����l�������V���ȓN�w�̎��H���K�v���A�ƍl����̂ł��B
------------------------------------------------
�|���F�Y���ɉ���Ċ��������� (�×с@��)
2011-12-03 14:36:28
�|���F�Y���͋ɂ߂ėD�ꂽ�N�w�̊w�ҁA���@�x�͓ˏo�����v�z�Ƃł����B���̂��Ƃ͊ԈႢ�Ȃ����̂Ǝv���܂��B���̓�l�̌��E�ɂ��Č�邱�Ƃ́A�N�w�E�v�z�̊j�S�ɐG��遁���P�����̒Nj��ɂȂ��邱�Ƃł�����ł��傤�B
�K�^�ɂ������g�A�^�P�Z������ɓ��s���āy���_�m�z�ɎQ�����A�|�����ɒ��ډ���Ęb�����邱�Ƃ��ł����̂ŁA���̖��̊j�S�ɐ��X�����G��邱�Ƃ��ł��܂����B
�ꖡ�s���b���グ���|�����̎v�l�ɂ͖ڂ����J������A�_���Ƃ��Ĕ��_�̗]�n���Ȃ����̂ł����B���A���̘_���̏G�킳�Ƌ��ɁA�����̈�a�������ĉ��܂����B
�c�_�̏ꂩ�痧�����镵�͋C�ɂ́A�v�l���̂��̂�b���グ�i���̂��̂Ƃ��鋭���ӎv���������A���t�Ƙ_���ɂ�鋭�łȍ\�z�����߂����Ă���Ƃ����l���� �����B�����ɁA���̋��łȐ��E�Ɏ������������鐶�X�����������E���͂ߍ������Ƃ���悤�Ȉ�a�A�������̓��퐢�E��ʐ��E������Ղ���悤�Ȉ�a�����͊� �����̂ł��B
��������ꂸ�ɂ����ƒP�������ɂ����A
�w�������D�ꂽ���E�ρi�v�z�j��_���I�ɍ\�z���邱�Ƃ͉\�ł���A���̐������v�z�ɂ���Č���������𐳂��Ă����˂Ȃ�Ȃ��B�x
�Ƃ���ϔO�ւ̈�a�ł��B
�������A�|�������g�̎v�z�͂��������ϔO��O�ꂵ�Ĕr��������̂ł��B����ɂ�������炸�A���������i���ꎊ���`�Ƃ��^����`�A���z�Ƃ������j���z�� ���t��ł͔ے肵�Ȃ���A���̂悤�Ȏv�z�Ɋׂ��Ă���悤�Ɍ����܂��B�����̑���X���������ł͂Ȃ��A����Ƙ_���ɂ���č\�������Ԑڌo���̐��E�� �u���A�ǂ����Ă��������E�i���ڌo���̐��E�j����Ղ��闧��Ɏ��g��ǂ�����ł��܂��̂ł��傤�B���́w�v�l�̓]�|�x��s�ގv�z�́A������ς��Ă����� ���́i�����̐l�X��[��������j�͂ɂ͐��蓾�Ȃ����A���g���ǓƂȐ��ɒǂ����ނق��Ȃ��A�Ǝ��ɂ͎v���܂��B
�|�����Ǝ��ۂɉ���Ęb�����Ă݂āA�������̂��Ƃ������܂����B
����͑�ϖ��Ȋ��v�ł��B�N�w��v�z�Ƃɂ��A�����Ŏ��Ȏ������߂����悤�Ƃ���A���ڌo���͌���Ȃ��ɂȂ�A�N�w��v�z�i�����ꂽ���́j���� �̐l�̐l���ɂƂ��čł��d�v�ʼn��l������̂ɂȂ�܂��傤�B���X�������������y�����ꂽ���́z�������Ƃ͕ʂ̍������̂��̂ƊŘ��ƂɂȂ�܂��B
�N�w�A�v�z�ƂƂ��Ȃ��܂ł��A����ɊS�������A�M�S�ɖ{��ǂސl�X�ɂ��������v���҂��\���Ă��܂��B
�悭�l���Ă݂�ƁA���́A�������̎���ł����̗��Ƃ����ɂ͂܂��Ă���l�X���������邱�ƂɋC�Â��܂��B���ڌo�����Ȃ܂ܒm����w��𗊂�Ɏd��������l�X�A����ɒm����w�m���l�ߍ��ގ������̎q�������̑��������łɓ��l�̕a�ɂƂ����Ă���悤�Ɏv���܂��B
���̗��Ƃ����A���ɂ͂܂邾���łȂ��A�[�֓I�D�z�ӎ��△���o�ȃG���[�g�ӎ����������錹��ɂ��Ȃ��Ă��邩��v���ӂł��ˁB
���X���������Ǝv�z�̊W���Ђ�����Ԃ��Ă͂Ȃ�܂���B�����ɍ����������̂Ȃ��Ɏv�z���ʒu�Â��Ȃ�������Ȃ��̂ł��B
�|������Ɖ���ĉ��߂Ď��͂����m�M���܂����B
���@�x�ɂ��Ă��G��悤�Ǝv�����̂ł����A�����Ȃ�̂ł�߂Ă����܂��i�j�B
�ꌾ�A�����^������́w���@�x ����Ǝv�z�x�ɐG���ƁA��͂蓯�l�́w�v�l�̓]�|�x������悤�Ɋ����܂����B�Ȃ�قǁA�������ɑ�ςȗ͍삾�Ǝv���܂����A�킩��ɂ����������ɂƂĂ����ɗ����܂����B
���A���@�x�̎v�z����I�K�R���Ƃ��đ�����̂ł͂Ȃ��A���܂��܂Ȏv�z�Ƃ̎v�z�i�����ꂽ���́j�̉e���ɂ��ď�����Ă���̂ŁA�ł��瑊�I�Ȉ�ۂ�@���܂���B
�ނ���A�ɂ߂ėD�ꂽ���y�Ƃł���A��w�ł���A��e�ł�����A���X���������𑫏�ɂ��Đ��������������q�Ƃ������݂��A���@�x�ɂǂ̂悤�ȉe����^�����̂��A���͑傢�ɋC�ɂȂ�܂��B
------------------------------------------------
�����N�w�錾 (���c�N�O)
2011-12-04 10:58:42
�×т����킽���́A�u���̓�l�̌��E�ɂ��Č�邱�Ƃ́A�N�w�E�v�z�̊j�S�ɐG��遁���P�����̒Nj��ɂȂ���v
�ƍl���āA�킽���̍l����y�̌��Ƃ��Ă̓N�w�z�̐c���������̂ł����A
����́A�y�����N�w�錾�z�ł�����܂��B
�l�Ԃ݂͂Ȏ�̎ҁi���N�w�ҁj�ł���A���҂ɗU������鑶�݂ł����Ă͂Ȃ�܂���B
�u���_�v�Ƃ��Ă̓N�w�͑O����̈╨�ł���A�g�����̂ɂȂ�܂���B�������E�ɂ�����u�̌������ρv�Ƃ��Ă̓N�w�i���X�̌o�������߁A������l�������A�L���ȈӖ���ǂݎ����H�j�́A�����Ƃ��Đ����邱�Ƃ��x���܂����A�����ɖ����`�̓y��ł�����܂��B
����!
------------------------------------------------
�N�w������� (���J�T��)
2011-12-04 08:35:08
�^�P�Z���̏m�œN�w����ǂ�ł������A�w�҂̕��Ƃ̓��_��Řb���Ă������A�x�X��N�w���Ă����Ɗ��o�I�Ȃ�Ȃ����Ȃ���Ɗ����邱�Ƃ�����܂����B�N�w�҂ƌĂ��l�B�̌������Ƃɂ́A�₽��Ɨ����������A�V�������t��T�O�������o�Ă��܂��B�ł��A���̌��t���Ė{���Ɏg���K�v��
����̂��H����ȊT�O������K�v������̂��H
����͂���Ō����Ă邱�Ƃ͕����邯�ǁA�����l�ɂ͂��̌��t���g�������A���_�����肽���Ƃ����C��������ɂ���悤�Ɋ����܂����B
�ł��N�w���邱�Ƃ��āA�{���͗����ł͂Ȃ��āA�����Ƃ����ƒP���ɁA����������Ƃ��ɔ��R�ƌ���̂łȂ��A�ڋʂ��Ђ�ނ��Ă�[������Ƃ��A�����Ƃ��͎��̌��������ۂ����Ă�[�������Ƃ��A�傫�����Ńn�L�n�L����Ƃ��A�������������Ƃ��Ǝv���܂��B
��������⌾�t�̑O�ɂ����ƃV���v���ŁA�����I�ŁA�����l�Ԃ�����Ǝv���܂��B��(�Ȃ�)�̌����Ŋ����A�z�������Ƃ��o���_�ɁA���R�ɁA�����悭 ����Ă����A�R�̂悤�ȗ����͂���Ȃ����A���e�͎��R�Ƙ_�����A�Ƃ����������͂��o�Ă���Ǝv���܂��B�_���A���_�Ƃ����̂͐�ɂ���A��ɋ��߂���̂� �͂Ȃ��A���ʂƂ��Đ��܂�Ă�����̂��Ƃ����̂��l�̊��o�ł��B
�����̂��旧�Ă��A�n�ʂ����_�����������̂ċ��������̐l��=�����Ƃ������݂���f���ɁA���̂܂܁A���āA�����āA������B���̕\�o�Ƃ��Č��t������̂��Ǝv���܂��B
�����āA������q�ǂ��͓N�w�҂ȂƎv���܂��B��l�������Ă���펯�◝���Ȃy�X��щz���Đ�����������璝��܂��B��l�������ꂽ���Ȃ��悤�ȁA�}�����Y�o�b�Ɠ˂��Ă��܂��B�{���͉����l���Ă��Ȃ��A�����������Ă��Ȃ����Ƃ��o���Ă��܂��}�������낵���I�m�ɁB
�l������ȗǂ��Ӗ��Ŏq�ǂ��̂悤�ȑ�l�ɂȂ肽���Ǝv���Ă��܂�������܂��܂����̂�͉�������ł��B
------------------------------------------------
�����̉��l�ςƐ����������o���� (�ؗ���)
2011-12-04 11:26:55
�N�w�������t�͂킩��܂��A�u����́y���z����i�̌��j�E�E�E�v�Ƃ����l�����ɂ͎^���ł��B
�����܂߂Ăł����A�����I�ɓ�����̑̌���v�z�Ő�����l�͏��Ȃ��̂ł͂Ȃ��̂ł��傤���B
�ƒ�A�w�Z�A�E��ł��u�O�̉��l�ρv����ɂ��āA���ꂪ������O�Ƃ��Đ������Ă���l���قƂ�ǂ��Ǝv���܂��B�܂��u�O�̉��l�ρv����ɂ��Đ����Ă���i�����Ă����j�Ǝ��o���邱�Ƃ����X�e�b�v�ł���ˁB����͂���Ȃɓ���Ȃ��ł��B
����̂́A���X�e�b�v�ł���u�O�̉��l�ρv�Ő����Ă������Ƃ����o������ŁA�����ňӎ����āu�ς��Ă����������̐��E��̌���[���@�艺���Ă����v���Ƃł��B
�����Ől�̐��������������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B���H����l�ƁA���H���Ȃ��l�B���H����ꍇ�A���X�̐����̒��ł��̍�Ƃ𑱂���
�����Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂ŁA�����܂ŁA�R�c�����ނ܂ŋꂵ���ł��B�ꂵ���Ƃ����̂͂��ꂾ�����܂Łu�O�̉��l�ρv�Ő����Ă�������A���̕Ȃ����ݕt���Ă��܂��Ă��邩��Ƃ������܂����B
�����ĕ����I�ɂ��W�c���������߂��Ă���Љ�Ő����Ă���ƁA�u���͎��v�Ǝ����ɑ���ւ�⑸�d�A�����炿�ɂ����̂ŁA�O���ɂ��鉿�l�ς����ɍ� �킹�Ă��܂����ƂŁu���v��}���i�ɒ[�Ɍ����u���v���E���j�A�����̐��E�Ƒ̌����炽�Ȃ��ɂȂ��Ă��܂��̂ł͂Ȃ��̂ł��傤���B������葼�ҁA�� �����{���Ɋ����Ă��邱�ƁE��肽�����Ƃ������Ԃ�Љ�F�߂Ă���E�������Ă��邱�Ƃ�D�悵�Ă����B��������Ɓu�O�̉��l�ρv����ɂ����������� �Ȃ��Ă��܂��Ǝv���܂��B
�厖�Ȃ͎̂����̉��l�ςƐ����������o����A�O→������ւƕς��Ă������Ƃł��ˁB
------------------------------------------------
���J����A���� (���c�N�O)
2011-12-04 12:46:05
���J���������̊����A�v���A�Ƃ��납��̎����̍l���A�����ł��ˁB
���܂ł��N�w���̗ނɂЂ��������Ă��Ȃ��ŁA
���X�̐������Ӗ��[���A���e�̔Z�����̂ɂ��邽�߂ɁA����N�w���邱�Ƃ��K�v�ł���ˁB
�N�w���ǂ݂̎�Ƃ��Ăł͂Ȃ��A�����̖L�`���̂��߂Ɏ����̓��ōl���遁�N�w���Ȃ���A�N�w�͖��p�̒����ǂ��납�A�l�Ԑ��_�����Ή�����A�C�e���ɂ����Ȃ�܂�����̂ˁB
���łɌ����A
�T���f�����ہ��Y�����ʔ���������o���Ė{���_�c�ɂ���ւ���u���_�V���[�v�����s����Ă̒m�̑ޔp�́A����N�w������H���Ȃ����Ƃ̏؋��ł��B
����
�O�Ȃ鉿�l�ӎ��ɔ���ꂽ�S�g����A
���Ȃ鐺���A������̐����߂�������H�Ɏ��g��ł���l�q���悭������܂��B�f���炵�����Ƃł��ˁB�ł炸�ɂ������i��ʼn������B
���{�l���K���ɂȂ�Ȃ������́A������́A�����I�Ȑ������߂��A��ϐ��̗͂�L���ɂ��邱�Ƃ�m��Ȃ�����ł����A����ɋC�Â����l������Ƒ����Ă� �܂��B�킪���{�Ƃ������́A�l���ɂ��ӎ��̎x�z�A���g�̐l�Ԃ��p�^�[���ɂ͂ߍ��܂�ĎE������l�ԓI�ȕ�����ς���̂́A�X�l�̐������i�O����ł͂Ȃ�������j �ł��B���ɁI
�@ �u���_�̓N�w�v����u�̌��̓N�w�v�ւ̐[���̂��߂ɁB