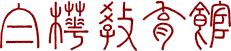19.松橋さんとの雑談会
|
||||
大分前のこと、2002年5月26日に白樺教育館にて、前にもご紹介した『柳兼子伝 -
楷書の絶唱 -』の著者 松橋桂子さんとの雑談会がありました。タイトルは[柳兼子の思い出話]。
とても少人数でざっくばらんな話を延々、ほとんど時間無制限で夜まで。
ちょっと時間が経ってしまいましたが今日はそのときのお話を少しお伝えします。
『柳兼子伝 - 楷書の絶唱 -』というすばらしい著作がなぜ生まれたのか、まずその辺の話から。松橋さんの動機を尋ねてみると。
 これほどの歌唱力を持った柳兼子という女性歌手は一体どんな人間であったろう。これほど魅力的な人間の生とはどんなものであったろう。多分それが個人的なきっかけだったと思う。
これほどの歌唱力を持った柳兼子という女性歌手は一体どんな人間であったろう。これほど魅力的な人間の生とはどんなものであったろう。多分それが個人的なきっかけだったと思う。
もう少し公的な話をすれば、日本の近代音楽史というものは歴史が浅く、とても乏しいものだったという止むを得ぬ事情がありました。特に声楽史はその傾向が顕著で、このあたり、もっと突っ込んだものが残せないだろうかという想いがありました。
もう一点、 柳宗悦(やなぎむねよし)のさまざまな活動は比較的研究され、よく知られたところとなっていますが、実際にその活動を支えていたのが柳兼子であったことはほとんど知られていません。このあたりをちゃんと伝えておきたかった。
『柳兼子伝 - 楷書の絶唱 -』を読めば、その論旨、動機が明確であることは良くわかります。一方で、その膨大で正確、緻密な資料をどうやって手に入れたのか、そのあたりの苦労もちょっと聞いてみました。
兼子がベルリンへ発ったとき、あちらで兼子を出迎える夫妻のフルネームがわからなくてかなり苦労しましたね。著述の中で次の一節があります。
『同年[1928(昭和3)年]4月26日京都発、朝鮮経由でドイツへの旅路につく。
・・・遂に兼子は憧れのベルリンの土を踏んだ。改札口では佐藤謙三と柴田経一郎・秀子夫妻が出迎えてくれた。』(柳兼子伝 p.157)
この事実を調べるため、麻布にある外交資料館で当時(70年ほど前)の海外渡航名簿(パスポート)の京都、新潟を調べまわってやっとわかったんです。
一つの例を挙げてみましたが、こうした作業を全編くまなくやったわけですね。気の遠くなるような作業です。書きたいことが非常に明確であること。それを実現するために手間暇を惜しまずエネルギーを注ぐ姿勢。私はウォルフレンの『日本権力構造の謎』にも通じるものがありますね、と尋ねると、私も武田さんの『1998年の私のエクリチュール』でウォルフレンを知り、大変共感を覚えました、と松橋さん。
|
教育、市民活動などタケセンのさまざまな活動の中で現した文書態(エクリチュール)をまとめたものです。 ご希望の方は送料込み1000円で
|
さて、柳兼子という女性が一体どんな人物であったか、これは『柳兼子伝』を読めばわかるのですが、このあたりもっと突っ込んで聞いてみました。
朝鮮で初めてのコンサートを催したのは27-28歳の頃。当時レパートリーが少なかったので学生時代、学友が習っていたソプラノの曲も歌ったりしていたようです。また二度目のコンサートの曲目に最初のコンサートで歌った曲目を選ぶことは決してしなかったといいます。このあたり、兼子の聴衆への誠意と意地が感じられます。
また、その昔、音楽大学に入るためには、受験の成績、実力というより、それ以前からの教授陣とのつながりが求められたそうです。受験時にはそれがモノをいったのですね。兼子はそのことを公然と批判していました。こんな話も紹介してくれました。
ある日、親子が兼子のもとを訪れる。もちろん受験を目当てに。兼子の対応はこんな感じだったそうです。
『将来性のある子供にどうして不純な思いをさせるのですか。お帰りなさい。』
こんな兼子でしたから、優秀な多くの弟子に恵まれることはありませんでした。実際、音楽界の一部からはかなり嫌悪され、国立音楽大学で教鞭をとりはじめたのは、62歳にからでした。途方もない力量を持っていましたから声楽界以外の著名な人たちからは高く評価されていましたが、声楽界では昔も今も兼子の声楽の能力はあまり認められていません。
その理由はもう一つありました。当時の声楽界といえば、欧米先進諸国の声楽を輸入して取り入れることが彼ら教授陣の財産だったのですが、兼子はそれとはまったく異なり、自分自身の内部に取り込んで昇華させるという本来の芸術家の王道を歩んでいたため、理解されないという面もありました。
東京下町で生まれた兼子の歯に衣着せない物言いは率直で真摯(しんし)であり、正当性に満ちており、当時の日本では中々受け容れられない性格であったようです。ただ一方でこんな一面もありました。
 当時は時代が時代ですから、芸術家であり、一女性であると同時に、母親であること、主婦であることも全(まっと)うしていました。宗悦(むねよし)に対しても言うべきことは言うが、常に一歩身を引き、従うという婦徳も備えていました。
当時は時代が時代ですから、芸術家であり、一女性であると同時に、母親であること、主婦であることも全(まっと)うしていました。宗悦(むねよし)に対しても言うべきことは言うが、常に一歩身を引き、従うという婦徳も備えていました。
さほど強烈な個性を持つ二人、兼子と宗悦の関係はどうだったのでしょう。
こんな会話がそれを象徴してるかもしれませんね。
- 生まれ変わったらとしたら誰と結婚しますか。
『もちろん柳よ。』
- あの世で宗悦さんに会ったらどうしますか。
『うらみつらみを全部言ってやるわ。』
宗悦は兼子に対し、常に『自分自身の芸術をなぜ追及しないのか。』と厳しく迫りながら、宗悦自身の活動、白樺派の活動を支えさせ、なおかつ主婦としても母親としても完璧さを要求していたようです。歌に関しては兼子を一度も褒(ほ)めたことがなかったといいます。
一方、柳といることで、(資金集めとしての)音楽活動を続けざるを得ず、芸術論を闘(たたか)わし、社会活動を続け、さまざまな優れた芸術家(バーナード・リーチや 志賀直哉、あるいは 河井寛次郎など)との交流をもてたのも事実でした。おそらくそれがなければ、兼子は自身の上り詰めた高みに至ることはなかったのでしょう。
柳宗悦は思索ばかりでなく、現実の中でさまざまな活動を続けてきましたが、事実上、それらはすべて兼子によって支えられてきたと言っても言い過ぎではないようです。
 ここに突出した生活者、創造者としての兼子と類稀(たぐいまれ)な知行合一の学者・思想家との稀有(けう)な出会いがあったと思われます。両者の関係は他人には知るすべもありません。
ここに突出した生活者、創造者としての兼子と類稀(たぐいまれ)な知行合一の学者・思想家との稀有(けう)な出会いがあったと思われます。両者の関係は他人には知るすべもありません。
言えることはこんなことでしょうか。
兼子に通り一片の幸せはなかったかもしれませんが、並みの人には想像も出来ない充実した創造活動を二人して織り上げてきたことは間違いのないところでしょう。
さて、本のタイトルは、『楷書の絶唱』ですが、【楷書】という文字が入っているのはなぜでしょうか。
兼子は母親から長唄や生け花などの習い事を最も厳しい先生につけられて徹底的に楷書を習わされたといいます。
字を崩すのはいつでも出来る。基礎がないと40過ぎて下る、というのが兼子の信念であったということです。実際に、そのように人生を全うし、最晩年の公演のときに次のように言っていたそうです。
80過ぎて(日本の歌に関しては)心が技術をしのぐようになった。落ちた体力をカバーするテクニックの発見に楽しみを覚えた。
これまでの日本歌曲唱法の積み重ねが 清瀬保二(きよせやすじ)の曲を歌うことですべて生きてきたと思う。
柳兼子の公式ステージの最後は、門下生と開いた『清瀬保二歌曲の夕べ』でしたが、兼子の歌はまさしく【楷書の絶唱】であったようです。何とも意味深くまたドンピシャのネーミングです。ちなみに、最晩年のこの公演は松橋さんにとってとても重要なものでした。何と言っても、敬愛して止まない柳兼子、そして松橋さんの師でもある清瀬保二(きよせやすじ)の曲目だったからです。この【柳兼子伝 - 楷書の絶唱 -】は清瀬保二と柳兼子の追悼事業という意味合いもあったようです。
 最後に、兼子が墓場まで持って行きたかったものを結果的に暴くような形になることはとても辛かったと松橋さんは言っていました。でもこんな話もあります。
最後に、兼子が墓場まで持って行きたかったものを結果的に暴くような形になることはとても辛かったと松橋さんは言っていました。でもこんな話もあります。
ある日、柳夫妻の共通の知人たちが[兼子と宗悦]談義をしていたそうです。
『兼子と宗悦、どっちが偉いかなぁ。』
『そりゃ、宗悦だろ。』
『さあ、それはどうかなぁ?』
この話を兼子が聞いて、『ホント、そうなの?』と何度もうれしそうに尋ねたといいます。
この話を聞くと、この著書が現れたことをきっと兼子は喜んでいるだろうと私は思います。ようやく姿を見せ始めた白樺派の一人、柳兼子の存在はこの著書なしにはありえないわけですから。
 参考:声楽リサイタル
\ 2,381円
参考:声楽リサイタル
\ 2,381円
作曲: 清瀬保二, 平井康三郎, その他
演奏: 柳兼子, 木村潤二
オーディオラボ レコード
CD番号 OVCA-00002
発売日2001年6月
1975年11月5日第一生命ホールにおける兼子83歳時のライブ。
超満員の聴衆からはすすり泣きする声も聞かれた。
2002年10月9日
2002年10月15日修正 古林 治